せどりで月5万円、10万円と利益が出始めた喜びも束の間、**「税金ってどうすればいいの…?」**という漠然とした不安が、あなたの頭をよぎっていませんか?
「副業は年間20万円までなら申告不要」という知識だけで、対策を後回しにしているとしたら、それは非常に危険なサインです。その知識は、あなたの状況に本当に合っていますか?知らないうちに脱税してしまい、ある日突然、利益が吹き飛ぶほどの追徴課税を課される未来は、絶対に避けたいはずです。
ご安心ください。この記事を最後まで読めば、あなたの税金に関する全ての不安は「自信」に変わります。
確定申告が必要になる明確な利益額から、Amazon手数料や梱包材を経費にする具体的な方法、そして会社にバレずに副業を続けるための住民税対策まで、あなたが本当に知りたかった情報を網羅しました。
税金は、あなたから利益を奪う「敵」ではありません。正しく理解すれば、手元に残るお金を最大化し、ビジネスをさらに加速させる**「最強の武器」**になります。
さあ、税金の不安から解放され、心からせどりを楽しみ、安心して利益を積み上げる未来への第一歩を、ここから踏み出しましょう。
1. 【結論】せどりで利益が出たら税金の支払いと確定申告は必須!
せどりで順調に利益が出始めると、大きな喜びと同時に「あれ、税金ってどうなるんだろう?」という疑問が浮かびますよね。
結論から断言します。せどりで一定以上の利益(所得)が出た場合、税金を納めること、そしてその金額を国に報告する「確定申告」は、すべての国民に課された義務です。
「なんだか難しそう…」「面倒くさいな…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。正しい知識を身につければ、確定申告は決して怖いものではありません。むしろ、あなたのビジネスを健全に成長させ、余計な税金を払わずに済む**「最強の盾」**となってくれます。
この章では、まず「そもそも自分は確定申告が必要なのか?」を判断できるよう、最も重要な基本ルールから解説していきます。
1-1. 副業なら年間利益20万円、専業なら48万円超えで確定申告が必要
あなたが確定申告をすべきかどうかは、まずこのボーダーラインを超えるかどうかで判断します。ご自身の状況に合わせて確認してみてください。
年間の利益(所得) = 1月1日〜12月31日の総売上 − 総経費
【副業の場合】会社員・パートなど給与をもらっている方
- せどりを含む給与以外の年間利益(所得)が20万円を超えた場合
- → 所得税の確定申告が「必要」です。
【専業の場合】個人事業主・学生・扶養内の主婦(主夫)など
- せどりでの年間利益(所得)が48万円を超えた場合
- → 所得税の確定申告が「必要」です。
- ※48万円は、すべての人に適用される「基礎控除」という割引額です。利益がこの金額を超えると、税金が発生する可能性が出てきます。
まずはこの「20万円」と「48万円」という数字を、あなたのスマホのメモ帳に登録しておきましょう。これが全ての基本となります。
1-2. なぜ20万円?超えなければ本当に何もしなくていい?
特に副業の方にとって重要な「20万円の壁」。これを超えなければ本当に何もしなくていいのでしょうか?
**答えは「NO」です。**ここに大きな落とし穴があります。
年間利益20万円以下で不要になるのは、あくまで国に納める**「所得税」の確定申告だけ。実は、あなたが住んでいる市区町村に納める「住民税」の申告は、利益が1円でも出ていれば別途必要**になるのです。
しかし、安心してください。所得税の確定申告を行えば、その情報が自動的に市区町村にも連携されるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。
つまり、利益が20万円以下の場合でも、
- 住民税の申告だけを別途行う
- 所得税の確定申告をして、住民税の申告もまとめて済ませる
のどちらかが必要になります。慣れない手続きを二度行うより、確定申告で一度に済ませてしまう方が結果的に楽だと言えるでしょう。
1-3. 確定申告をしないとどうなる?無申告加算税・延滞税の重いペナルティ
「少しくらいならバレないだろう…」その油断が、数年後に大きな後悔を生む可能性があります。税務署は、Amazonや楽天といったプラットフォーム事業者に対し、販売者の取引データを照会する権限を持っています。つまり、誰が・いつ・いくら売ったかは、あなたが思うより簡単に把握されているのです。
もし確定申告をせず、後から税務調査で無申告が発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のような重いペナルティが課せられます。
- 無申告加算税
- 納税を怠った罰金。本来の税額に対し**最大20%**が上乗せされます。
- 延滞税
- 納付が遅れた日数に応じてかかる利息。年率は最大14.6%(2025年時点)と非常に高金利です。
- 重加算税
- 意図的に所得を隠すなど、悪質だと判断された場合に課される最も重い罰金。税額は**最大40%**にもなります。
本来10万円で済んだはずの税金が、これらのペナルティによって合計で20万円近くに膨れ上がるケースも珍しくありません。せっかく稼いだ利益を罰金で失うことほど、もったいないことはありません。
1-4. 税金は「利益(所得)」に対してかかる!売上ではない
最後に、税金計算における最も重要な大原則をお伝えします。それは、税金は「売上」ではなく、そこから経費を差し引いた「利益(所得)」に対してかかるということです。
利益(所得) = 売上 - 経費
このシンプルな計算式を絶対に忘れないでください。
例えば、年間の売上が100万円だったとしても、商品の仕入れ代や送料などの経費が90万円かかっていれば、あなたの利益(所得)は10万円です。この場合、副業の会社員なら「20万円の壁」を下回るため、所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は必要)。
逆に、年間の売上が30万円でも、経費が5万円しかかかっていなければ、利益(所得)は25万円。この場合は「20万円の壁」を超えるため、確定申告が必要になります。
つまり、どんなものを経費として正しく計上できるかを知っているかどうかが、あなたが支払う税金の額を大きく左右するのです。次の章では、この「経費」にできるものについて、具体的に詳しく解説していきます。
2. あなたはどっち?事業所得と雑所得の境界線と選び方
せどりで得た利益(所得)は、確定申告の際に**「事業所得」または「雑所得」**のどちらかに分類して申告する必要があります。
「どっちも同じじゃないの?」と思うかもしれませんが、この選択はあなたが支払う税金の額に天と地ほどの差を生む可能性がある、非常に重要な分かれ道です。
簡単に言うと、本気で稼ぎ、節税したいなら「事業所得」、**お小遣い稼ぎの範囲なら「雑所得」**となります。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、あなたに最適な選択をしましょう。
2-1. 「事業所得」と「雑所得」の違いを徹底比較|メリット・デメリット一覧表
まずは、2つの所得区分が具体的にどう違うのか、一覧表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 事業所得 (Business Income) | 雑所得 (Miscellaneous Income) |
| 位置づけ | 継続的・安定的な本業または副業 | 一時的・偶発的なお小遣い稼ぎ |
| 青色申告 | 可能(最大の節税メリット) | 不可 |
| 赤字の扱い | 損益通算ができる(給与等と相殺) | 損益通算はできない |
| 赤字の繰越 | 3年間繰り越しが可能 | 繰り越しはできない |
| 帳簿付け | 原則、複式簿記(会計ソフトを使えば簡単) | 簡易な帳簿でOK |
| 必要な届出 | 開業届の提出が必須 | 不要 |
この表で最も注目すべきは、**「青色申告」と「損益通算」**です。これらは「事業所得」だけに認められた強力な節税の武器であり、後ほど詳しく解説します。
2-2. 開業届を出すかどうかが最大の分かれ目
「事業としてやっているか」の法的な判断基準はいくつかありますが、あなたが手続き上、最も意識すべき分かれ目は「開業届」を税務署に提出するかどうかです。
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出することで、あなたは正式に「個人事業主」となり、せどりの利益を**「事業所得」**として申告する意思表示をしたことになります。
逆に、この開業届を提出していなければ、せどりの利益は原則として**「雑所得」**として扱われます。
つまり、あなたが「事業所得」のメリットを享受したいと考えるなら、まず開業届の提出がスタートラインになる、と覚えておきましょう。
2-3. 副業会社員におすすめは?最初は「雑所得」でもOK?
「じゃあ、せどりを始めたらすぐに開業届を出さないといけないの?」と不安に思った副業会社員の方、ご安心ください。
結論として、せどりを始めたばかりで利益もまだ少ないうちは、無理に開業届を出さず「雑所得」として申告する形で全く問題ありません。
まずは気軽に始めてみて、年間利益が安定して20万円を超えるようになった、または**「これから本気でせどりを大きくしていくぞ!」と決意したタイミング**で、開業届を提出し「事業所得」に切り替えるのが、最もスムーズで賢い方法です。
最初はシンプルに「雑所得」で確定申告に慣れ、ビジネスが軌道に乗ってきたら節税メリットの大きい「事業所得」へステップアップしましょう。
2-4. 赤字を給与と相殺できる「損益通算」は事業所得だけの特権
「事業所得」を選ぶ最大のメリットの一つが、この**「損益通算(そんえきつうさん)」**です。
これは、もしせどりで赤字が出てしまった場合、その赤字額を給与などの他の黒字所得から差し引くことができるという、非常に強力な制度です。
言葉だけでは分かりにくいので、具体例で見てみましょう。
【例】年収500万円の会社員が、副業のせどりで年間30万円の赤字を出してしまった場合
- ① 雑所得で申告した場合
- せどりの赤字30万円は無かったことにされます。
- 課税対象となる所得は、給与所得の500万円のまま。税金は安くなりません。
- ② 事業所得で申告した場合(損益通算アリ)
- 給与所得500万円から、せどりの赤字30万円を差し引くことができます。
- 課税対象となる所得は 470万円(500万円 – 30万円)に圧縮されます。
- 結果:所得が減るため、すでに源泉徴収で天引きされていた所得税の一部が「払い過ぎ」となり、確定申告によって手元に還付(返金)されます。
このように、万が一赤字になった場合でも、事業所得なら給与から天引きされた税金を取り戻すことができるのです。このリスクヘッジ効果は、雑所得にはない、事業所得だけの特権と言えます。
3. 【最重要】せどりで経費にできるもの・できないもの全リスト
納める税金を減らす最もシンプルで、かつ最も強力な方法。それが**「経費を漏れなく計上すること」**です。
売上 - 経費 = 利益(所得)
この計算式を思い出してください。経費を1円でも多く計上できれば、その分利益(所得)が圧縮され、結果としてあなたが支払う税金は安くなります。
経費として認められるための大原則はたった一つ。**「せどり事業で利益を上げるために、直接必要だった費用」**であることです。この原則に沿って、具体的にどんなものが経費になるのか、徹底的にリストアップしました。ご自身の支出と照らし合わせながら確認していきましょう。
3-1. 仕入れ関連の経費(商品代金、送料、関税)
せどりの根幹となる、商品の仕入れにかかる費用です。
- 商品仕入代金店舗せどりで購入した商品の代金や、電脳せどりで支払った商品代金です。クレジットカードの明細や銀行の振込記録も重要な証拠になります。
- 仕入れ時の送料ネットショップからの送料や、海外から商品を輸入する際にかかった国際送料などです。
- 関税・輸入消費税海外から商品を輸入した場合に、税関で支払った関税や輸入消費税も経費として計上できます。
3-2. 販売・発送関連の経費(プラットフォーム手数料、梱包材、配送料)
商品が売れてから、お客様の手元に届くまでにかかる費用です。
- 販売手数料(プラットフォーム手数料)Amazonの販売手数料、FBA手数料、楽天市場の出店料、メルカリShopsの販売手数料など、各プラットフォームに支払うすべての手数料が含まれます。
- 梱包資材費ダンボール、ガムテープ、緩衝材(プチプチ)、OPP袋、封筒、ラベルシールなど、商品を梱包するために購入した備品代です。
- 配送料ゆうパック、宅急便、クリックポストなど、お客様へ商品を発送するために支払った送料です。
3-3. 業務効率化のための経費(ツール代、情報商材費、セミナー参加費)
「こんなものまで?」と思うかもしれませんが、事業の成長に必要な自己投資やツール代も立派な経費です。
- ツール利用料価格改定ツール(プライスター、マカドなど)、在庫管理ツール、出品ツール、リサーチツールなどの月額・年額費用。
- 情報収集費(新聞図書費)せどりのノウハウに関する書籍、雑誌、有料noteやBrainなどの情報商材の購入費用。
- 研修費せどりの勉強会や有料セミナーの参加費、コンサルティングを受けた場合の費用。
3-4. 通信・移動関連の経費(スマホ・ネット代、ガソリン代、駐車場代)
プライベートと兼用することが多い費用ですが、事業で使った分は経費にできます。
- 通信費商品リサーチや出品作業で使うインターネットのプロバイダ料金、スマートフォンの利用料金、Wi-Fiルーターの費用など。
- 交通費店舗仕入れのために移動した際の電車代、バス代、タクシー代など。SuicaやPASMOの利用履歴も証拠になります。
- 車両関連費仕入れに自家用車を使う場合のガソリン代、高速道路代、コインパーキング代、さらには自動車税、車検代、保険料なども後述する「家事按分」により経費にできます。
3-5. 自宅兼事務所の経費(家賃、光熱費)を按分する方法
在宅でせどりを行う方にとって、最大の節税ポイントがこの**「家事按分(かじあんぶん)」**です。
家事按分とは、家賃や電気代のように**「事業での利用」と「プライベートでの利用」が混在している支出**を、合理的な基準で分け、事業で使った割合分だけを経費として計上することを言います。
【家事按分の具体例】
- 家賃(地代家賃)基準:事業で使っている部屋の面積
**計算例:**家全体の面積が60㎡で、作業・在庫保管部屋が15㎡の場合 → 15㎡ ÷ 60㎡ = 25%。家賃10万円なら、2.5万円を経費にできます。
- 電気代(水道光熱費)基準:事業で使っている時間やコンセントの数
**計算例:**1日のうち8時間をせどり作業に充てている場合 → 8時間 ÷ 24時間 = 約33%。電気代1.5万円なら、5,000円を経費にできます。
- 通信費基準:事業での使用時間
**計算例:**スマートフォンの利用時間のうち、半分がリサーチや連絡などの事業利用の場合 → 50%。スマホ代1万円なら、5,000円を経費にできます。
重要なのは、「なぜその割合にしたのか?」を税務署に説明できる客観的で合理的な基準を持つことです。自分なりのルールを決めて、メモに残しておきましょう。
3-6. 間違えやすい!経費にできないものの具体例
節税意識が高まるあまり、何でも経費にしたくなりますが、認められないものも存在します。以下は代表的な例です。
- 事業主個人のための支出一人で食べたランチ代、スーツ代(事業専用と明確に区別できないため原則不可)、事業主自身の健康診断や生命保険料など。
- 税金関連所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金。
※国民健康保険料と国民年金は経費にはなりませんが、**「社会保険料控除」**という形で所得から差し引くことができ、結果的に節税につながります。
- 罰金・科料仕入れの際の駐車違反の罰金など。
3-7. 証拠が命!領収書・レシートの正しい保存方法
どんなに多くの経費を計上しても、その支払いを証明する**証拠(領収書やレシートなど)**がなければ、税務調査の際に否認されてしまいます。
- 保存すべきもの領収書、レシート、クレジットカードの利用明細、銀行の振込明細、請求書、納品書、各種契約書など、お金の動きがわかるもの全て。
- 保存期間(2025年8月時点)
- 白色申告の場合:5年間
- 青色申告の場合:7年間
- 具体的な保存方法月ごとに封筒やクリアファイルに分けたり、ノートに日付順に貼り付けたりするのが基本です。レシートの感熱紙は文字が消えやすいため、コピーを取るか、スキャナで読み込んでデータ保存(※電子帳簿保存法の要件を確認)するのも良い方法です。
【プロのコツ】
レシートの余白に**「〇〇(店舗名)にて梱包用ダンボール購入」「〇〇氏との打ち合わせ飲食代」**のように具体的な内容をメモしておくと、後から見返したときに何に使った費用か一目瞭然となり、非常に管理が楽になります。
4. 利益と納税額の計算方法|具体例でシミュレーション
「利益はわかったけど、結局いくら税金を払うの?」ここからは、その計算方法を具体的に解説します。一見複雑に見えますが、4つのステップに沿って進めれば、誰でも自分の納税額を計算できます。
専門家でなくても理解できるよう、一つひとつ丁寧に説明しますので、ぜひあなたの状況に置き換えて読み進めてみてください。
4-1. STEP1:売上を計算する(Amazon、楽天、メルカリなど)
まず最初に、1月1日から12月31日までの1年間に、お客様から受け取ったお金の総額、つまり**「売上」**を計算します。
- Amazonならセラーセントラルのペイメントレポート
- 楽天ならRMSの売上レポート
- メルカリShopsなら売上管理画面
など、利用しているすべてのプラットフォームの販売者向け画面を確認し、年間の売上を合算しましょう。ここで計算するのは、手数料などが引かれる前の**「総売上」**です。
4-2. STEP2:経費を計算する
次に、STEP1の売上を上げるためにかかった**「経費」**をすべて合計します。
前の章で解説した「経費にできるものリスト」を参考に、1年分のレシートやクレジットカード明細を集計しましょう。会計ソフトを使っている場合は、自動で集計されているはずです。
ここで、せどりの**利益(所得)**が確定します。
せどりの利益(所得) = STEP1の総売上 - STEP2の総経費
この利益(所得)の金額が、税金計算の土台となります。
4-3. STEP3:課税所得を計算する(売上 – 経費 – 所得控除)
STEP2で計算した利益(所得)の全額に税金がかかるわけではありません。国は個人の事情を考慮して、税金の対象となる金額を減らしてくれる**「所得控除」**という割引制度を用意しています。
課税所得 = 利益(所得) - 所得控除の合計額
所得控除には、以下のようなものがあります。
- 基礎控除: 全員が一律で受けられる48万円の控除
- 社会保険料控除: 支払った国民年金や国民健康保険料の全額
- 扶養控除: 扶養している親族がいる場合の控除
- 生命保険料控除: 生命保険料を支払っている場合の控除
- 青色申告特別控除:(事業所得の場合)最大65万円の控除
これらの「所得控除」を利益(所得)から差し引いた金額、それが最終的に税率を掛ける**「課税所得」**です。
4-4. STEP4:所得税額を計算する(課税所得 × 税率 – 税額控除)
いよいよ最後のステップです。STEP3で計算した「課税所得」に、所得税の税率を掛けて納税額を計算します。所得税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる**「累進課税」**が採用されています。
所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額
【所得税の速算表(2025年8月時点)】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5%1 | 0円2 |
| 195万円超 330万円以下3 | 10%4 | 97,500円5 |
| 330万円超 695万円以下6 | 20%7 | 427,500円8 |
| 695万円超 900万円以下9 | 23%10 | 636,000円11 |
| 900万円超 1,800万円以下12 | 33%13 | 1,536,000円14 |
| 1,800万円超 4,000万円以下15 | 40%16 | 2,796,000円17 |
| 4,000万円超18 | 45%19 | 4,796,000円20 |
例えば、課税所得が300万円の場合、上の表の「195万円超 33021万円以下」にあてはまるので、計算式は
300万円 × 10% – 97,500円 = 202,500円
となり、所得税額は202,500円となります。
4-5. 【具体例】年収500万円の会社員が副業せどりで年間利益50万円を得た場合の納税額
それでは、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
- 前提条件
- 年収(給与収入):500万円
- せどりの利益(所得):50万円(雑所得で申告)
- 年齢:40歳、独身(扶養親族なし)
- 所得控除:基礎控除48万円、給与から天引きされた社会保険料70万円
この場合、給与所得とせどりの所得を合算して税金を再計算します。
- 給与所得の計算: 500万円(給与収入) – 144万円(給与所得控除) = 356万円
- 合計所得の計算: 356万円(給与所得) + 50万円(せどり所得) = 406万円
- 課税所得の計算: 406万円(合計所得) – 48万円(基礎控除) – 70万円(社会保険料控除) = 288万円
- 所得税額の計算: 288万円(課税所得) × 10% – 97,500円 = 190,500円
この方がせどりをしていなければ、所得税額は約14万円です。つまり、せどりで50万円の利益を得たことで、追加で納める所得税は約5万円になる、という計算です。
※上記は簡略化した計算です。実際の金額は源泉徴収票や控除額により変動します。
4-6. 所得税だけじゃない!住民税と個人事業税も忘れずに
確定申告で計算するのは主に「所得税」ですが、私たちが支払う税金はそれだけではありません。
- 住民税確定申告をすれば、その情報に基づいてお住まいの市区町村が税額を計算し、翌年6月頃に納付書を送ってきます。税率は、所得に対して**一律およそ10%**です。上記の例では、せどりの利益50万円に対して約5万円の住民税が追加でかかります。
- 個人事業税これは**「事業所得」として申告し、かつ年間の利益が290万円を超えた場合にのみかかる税金です。せどりのような物品販売業の場合、税率は5%**です。副業の範囲であれば、ほとんどの方が対象外となりますので、頭の片隅に置いておく程度で大丈夫です。
5. 青色申告 vs 白色申告|節税効果が高いのはどっち?
せどりの利益を「事業所得」として申告すると決めたら、次にあなたは確定申告の方法を**「青色申告」と「白色申告」**の2つから選ぶことになります。
「また新しい言葉が…」と身構える必要はありません。この選択は非常にシンプルです。
結論から申し上げます。あなたが本気でせどりで稼ぎ、手元に残るお金を1円でも多くしたいと考えるなら、「青色申告」を選ばない手はありません。
その圧倒的な節税効果を理解するために、まずは簡単な「白色申告」から見ていきましょう。
5-1. 白色申告のメリット・デメリット|帳簿付けが簡単
白色申告は、いわば確定申告の**「スタンダードモード」**です。
- メリット
- とにかくシンプル: 帳簿付けはお小遣い帳レベルの簡単な記録(単式簿記)で済み、税務知識がなくても比較的とっつきやすいのが最大のメリットです。
- 事前申請が不要: 後述する青色申告のような事前の届出は必要ありません。青色申告の申請をしなければ、自動的に白色申告になります。
- デメリット
- 節税メリットがほぼ無い: 青色申告にあるような、税金が劇的に安くなる特別な割引(控除)が一切ありません。
白色申告は、**「利益がまだごく僅かなので、とにかく手間をかけずに申告を済ませたい」**という方向けの、シンプルな選択肢と言えます。
5-2. 青色申告のメリット・デメリット|最大65万円の特別控除が魅力
青色申告は、きちんと帳簿付けをする個人事業主を国が応援してくれる、いわば**「節税の優遇制度」**です。
- メリット(代表的な3つ)
- 青色申告特別控除(最大65万円): これが最大の魅力です。売上から経費を引いた利益(所得)から、さらに最大65万円を差し引くことができます。例えば、利益が100万円でも、この控除を使えば課税対象は35万円(100万円 – 65万円)にまで圧縮され、税金が劇的に安くなります。
- 赤字の3年間繰越し: もし事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。これにより、好不調の波があるビジネスでもトータルでの納税額を抑えられます。
- 家族への給与を経費にできる: 配偶者や親族が事業を手伝っている場合、その方へ支払う給与を「青色事業専従者給与」として全額経費にできます(※要件あり)。
- デメリット
- 事前申請が必要: 青色申告をするためには、定められた期限内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
- 複式簿記での記帳: 最大65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」という正規のルールに則った帳簿付けが必要です。
「複式簿記」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、次の項目で解説する**「あるもの」**を使えば、簿記の知識がゼロでも全く問題ありません。
5-3. 青色申告65万円控除を受けるための3つの条件(e-Taxは必須)
青色申告の最大のメリットである「65万円控除」を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 複式簿記で記帳していること日々の取引を正規の簿記ルールで記録している必要があります。
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること確定申告書に、複式簿記で作成した決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付して提出します。
- e-Taxによる電子申告 または 優良な電子帳簿保存作成した確定申告書を、**インターネット経由で提出(e-Tax申告)**します。もし紙で印刷して税務署に提出した場合、控除額は55万円に減額されてしまうため注意が必要です。
この3つの条件、特に「複式簿記」や「決算書」という言葉に、アレルギー反応を起こす必要はありません。
5-4. 初心者でも大丈夫!会計ソフトfreeeやマネーフォワードを使えば青色申告は怖くない
簿記の知識がない初心者が、青色申告の条件を自力でクリアするのは困難です。しかし、**「クラウド会計ソフト」**を使えば、そのハードルは一気に解消されます。
代表的なソフトは**「freee(フリー)」や「マネーフォワード クラウド確定申告」**です。
【会計ソフトがすべて解決してくれること】
- 面倒な記帳を自動化: 銀行口座やクレジットカードを連携すれば、取引明細を自動で取得。あなたは簡単な質問に答えるだけで、ソフトが自動で複式簿記の形式に変換してくれます。
- 決算書を自動作成: 日々の入力さえ済ませておけば、確定申告に必要な「貸借対照表」や「損益計算書」はボタン一つで自動作成されます。
- 確定申告をナビゲート: 画面の指示に従って質問に答えていくだけで、確定申告書が完成。そのままe-Taxでの提出までをサポートしてくれます。
月々1,000円〜2,000円程度の利用料はかかりますが、65万円の控除で得られる節税額(所得税・住民税合わせて数万円〜十数万円)を考えれば、圧倒的にお得な自己投資と言えるでしょう。
5-5. 青色申告承認申請書の提出期限と書き方
青色申告を始めるには、まず「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
- 提出期限
- 原則: 青色申告をしたい年の3月15日まで。(例:2025年分の確定申告を青色で行いたい場合 → 2025年3月15日までに提出)
- 年の途中で開業した場合: 事業を開始した日(開業日)から2ヶ月以内。
- 申請書の入手と書き方
- 入手方法: 国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。
- 書き方のポイント:
- 納税地や氏名など基本情報を記入します。
- 「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」には屋号と自宅住所などを記入。
- 所得の種類は「事業所得」。
- 最重要: 簿記方式は必ず**「複式簿記」**にチェックを入れます(ここにチェックしないと65万円控除は受けられません)。
- 提出先: あなたの住所地を管轄する税務署。
せどりを事業として本格的に始める方は、「開業届」と一緒にこの「青色申告承認申請書」を提出するのが最も効率的でおすすめです。
6. 【2025年最新】消費税とインボイス制度、せどりの対応策
ここまでの話は、個人の利益に対してかかる**「所得税」の話でした。この章では、もう一つの重要な税金「消費税」**について解説します。
かつて、個人事業主の多くにとって消費税は「年間売上が1,000万円を超えてから考えればいいもの」でした。しかし、2023年10月にスタートした**「インボイス制度」**によって、その常識は完全に変わりました。
今や、売上規模に関わらず、すべてのせどり実践者がインボイス制度を正しく理解しておく必要があります。あなたの事業戦略や利益に直結する、非常に重要な知識です。
6-1. 年間売上1,000万円を超えたら消費税の納税義務が発生
まずは消費税の基本ルールから押さえましょう。
事業者が消費者から預かった消費税を国に納める義務があるかどうかは、「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで決まります。
- 基準期間とは: 原則として2年前の1月1日〜12月31日までの期間
- 課税売上高とは: せどりの場合、消費税が課税される商品の年間総売上のこと
【具体例】
2023年の年間売上が1,200万円だった場合
→ 2年後の2025年から、あなたは**「課税事業者」**となり、2025年中の取引で預かった消費税を国に納める義務が発生します。
逆に、この基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は**「免税事業者」**といい、原則として消費税の納税が免除されています。
6-2. インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録すべき?判断基準を解説
「自分の売上は1,000万円以下だから関係ない」と思っていませんか?インボイス制度の開始により、その考えは通用しなくなりました。
インボイス制度を簡単に言うと:
事業者が、仕入れなどで支払った消費税分の控除(仕入税額控除)を受けるためには、取引相手から**登録番号が記載された「適格請求書(インボイス)」**をもらう必要がある、という新ルールです。
【せどり事業者にとっての最大の問題点】
この「適格請求書(インボイス)」を発行できるのは、税務署に申請し、登録を受けた**「適格請求書発行事業者」**だけです。そして、この登録事業者になるためには、売上が1,000万円以下であっても、強制的に「課税事業者」になる必要があります。
では、あなたは登録すべきなのでしょうか?
判断基準は、**「あなたの主なお客様は誰か?」**という一点に尽きます。
- ケースA:お客様が一般の個人消費者(BtoC)の場合Amazonや楽天、メルカリShopsなどで一般ユーザー向けに販売している場合、お客様は消費税の控除など考えません。したがって、インボイスの発行を求められることはまずありません。
→ 結論:登録する必要性は低い
- ケースB:お客様が法人や個人事業主(BtoB)の場合卸売や、企業向けに商品を販売している場合、取引相手は消費税の控除ができないと困ります。あなたがインボイスを発行できないと、**「取引を打ち切られる」「消費税分の値引きを要求される」**といった事態になりかねません。
→ 結論:登録を強く推奨
ほとんどのせどり実践者はケースAに該当するため、慌てて登録する必要はないと言えるでしょう。
6-3. Amazon、メルカリShopsなどプラットフォーム毎のインボイス対応まとめ
あなたが利用しているプラットフォームがインボイス制度にどう対応しているかを知っておくと、より安心です。
- Amazonインボイス発行事業者が登録を行うと、事業者情報に登録番号が表示されます。法人・個人事業主のお客様からの注文には、Amazonが事業者に代わって適格請求書(領収書)を自動で発行してくれます。
- 楽天市場出店者がインボイス発行事業者である場合、購入者が購入履歴から適格請求書をダウンロードできる仕組みが整備されています。
- メルカリShopsインボイス発行事業者として登録したショップには、その旨を示すラベルが表示されます。購入者は、必要に応じて店主(あなた)にインボイスの発行を依頼する形になります。
- Yahoo!ショッピング、ヤフオク!同様に、インボイス発行事業者の登録・表示機能が備わっています。
各プラットフォームは制度に対応済みですが、あなたが登録すべきかどうかは、あくまであなたのビジネスモデル(お客様が誰か)次第という点は変わりません。
6-4. あえて登録しない戦略と今後の展望
ここまでの話をまとめると、売上1,000万円以下のせどり実践者にとっての最適な戦略が見えてきます。
【基本戦略】
お客様が一般消費者である限り、インボイス制度には登録せず、「免税事業者」のままでいる。
【登録しないメリット】
- 消費税の納税義務がない: これが最大のメリットです。お客様から預かった消費税は、納税せずにそのまま事業者の利益(益税)となります。
- 事務負担が増えない: 消費税の申告・納税という、複雑で面倒な手続きから解放されます。
【今後の展望と注意点】
インボイス制度はまだ過渡期です。今後、政府の方針やプラットフォームの規約が変更される可能性はゼロではありません。
しかし、2025年8月現在においては、**「BtoCに徹して免税事業者のメリットを最大限に享受する」**ことが、売上1,000万円以下のせどり事業者にとって最も賢い立ち回り方と言えるでしょう。もし事業が拡大し、売上が1,000万円のラインが見えてきた段階で、課税事業者になる準備を始めれば十分です。
7. せどりの税金に関するQ&A|よくある疑問を解消
ここまでの章で、せどりの税金に関する基本的な知識は一通り網羅できました。しかし、実際に取り組んでいると「こんな時はどうするの?」という、より具体的な疑問が湧いてくるはずです。
この章では、多くの方が抱える「よくある質問」にQ&A形式でズバリお答えし、あなたの最後の不安を解消していきます。
7-1. 会社に副業せどりがバレないようにするには?住民税の「普通徴収」が鍵
副業せどらーにとって最大の懸念事項、それは「会社にバレないか?」でしょう。会社が副業を把握する最大のきっかけは、税務署からの連絡ではなく**「住民税」の金額**です。
- バレる仕組み(特別徴収):通常、会社はあなたの給与から住民税を天引き(特別徴収)しています。あなたが副業で稼ぐと、その利益の分だけ住民税が増額され、その通知が会社の給与担当者に届きます。「〇〇さんの住民税が、給与計算上の金額より高いのはなぜ?」と疑問に思われるのが、副業がバレる王道パターンです。
- バレなくする対策(普通徴収):この仕組みを回避する方法があります。確定申告書を作成する際、第二表の「住民税に関する事項」という欄に、**「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する項目があります。
ここで「自分で納付」(普通徴収)**に必ずチェックを入れてください。
こうすることで、せどり分の住民税の納付書だけが、会社の給与から天引きされず、あなたの自宅に直接郵送されるようになります。会社には給与分の住民税額しか通知されないため、副業が発覚するリスクを劇的に下げることができます。
※注意: この方法はリスクを大幅に減らしますが、100%ではありません。自治体によっては対応が漏れる可能性もゼロではないこと、また会社の就業規則で副業が禁止されていないか、事前に確認しておくことも重要です。
7-2. 確定申告の期間はいつからいつまで?遅れたらどうなる?
- 申告期間:確定申告の期間は、原則として利益が出た翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。
(例:2025年1月1日〜12月31日の利益 → 2026年2月16日〜3月15日に申告)
- 遅れた場合:もし期限を過ぎてしまっても、絶対に放置してはいけません。1日でも早く**「期限後申告」をしましょう。ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」**が課せられますが、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティが軽減される措置があります。気づいた時点ですぐに申告することが、被害を最小限に抑える鍵です。
7-3. 赤字になった場合も確定申告はした方がいい?
「利益が出ていないなら申告は不要」と考えるのは早計です。赤字でも確定申告をした方が断然お得になるケースがあります。
- 事業所得で申告している場合:
- 損益通算ができる: サラリーマンの副業の場合、せどりの赤字を給与所得と相殺できます。これにより、給与から天引きされた所得税の一部が戻ってくる(還付される)可能性があります。
- 損失を繰り越せる(青色申告のみ): 青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。翌年以降に利益が出た際に、過去の赤字と相殺して納税額を減らすことができます。
これらのメリットを享受するために、たとえ赤字であっても確定申告をすることをおすすめします。
7-4. 税務調査はどんな時に来る?個人でも油断は禁物
税務調査は、大企業や巨額の利益を上げている個人だけが対象ではありません。個人のせどり事業主であっても、調査対象になる可能性は十分にあります。
【税務調査の主なきっかけ】
- Amazonなどのプラットフォーム上で大きな売上があるのに、申告がない。
- 売上に対して、経費の割合が異常に高い。
- 毎年ギリギリ赤字など、不自然な申告が続いている。
- 第三者からのタレコミ(通報)。
- 無作為抽出による調査。
税務調査で慌てないための最善の対策は、日頃から正しい帳簿付けを行い、すべての領収書や請求書をきちんと保管し、誠実な申告を続けることです。これさえできていれば、何も恐れることはありません。
7-5. 学生や扶養内の主婦(主夫)がせどりをする場合の注意点
学生や扶養に入っている主婦(主夫)の方がせどりをする場合、ご自身の税金だけでなく、扶養者(親や配偶者)の税金にも影響が出るため、特に注意が必要です。
- 所得税の扶養(103万円の壁):これはアルバイトなどの給与収入がある場合の話です。せどりのような事業の場合、年間利益(所得)が48万円を超えると、扶養から外れ、扶養者の税金(所得税・住民税)が高くなります。
- 社会保険の扶養(130万円の壁):こちらがより重要です。年間の収入(せどりの場合は利益)が130万円を超えると見込まれる場合、社会保険の扶養からも外れます。そうなると、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料(年間で数十万円)を支払う義務が生じ、家計へのインパクトは非常に大きくなります。
扶養の範囲内で活動したい場合は、これらの「壁」を意識して、利益をコントロールすることが重要です。
7-6. 古物商許可証は税金に関係ある?
**結論から言うと、全く関係ありません。**この2つは完全に別次元の話です。
- 古物商許可証:中古品をビジネスとして売買するために、警察署から受ける許可です。これは古物営業法という法律に基づくもので、盗品などの流通を防ぐ防犯が目的です。
- 税金(確定申告):事業で得た利益を計算し、税務署に申告・納税することです。これは所得税法などの税法に基づく、国民の義務です。
「許可証を持っているから税金は大丈夫」「許可証がないから申告しなくていい」といった考えは、どちらも間違いです。中古品せどりを行うなら「警察への許可」と「税務署への申告」は、それぞれ独立した義務として両方果たさなければなりません。
8. 今からできる!せどりの合法的な節税テクニック5選
経費を漏れなく計上するのは、いわば節税の「守り」です。この章では、さらに一歩進んで、合法的な制度を賢く利用して納税額を積極的にコントロールする**「攻めの節税」**テクニックを5つ厳選してご紹介します。
これらの制度を知っているか知らないかで、数年後に手元に残るお金が数十万円、数百万円単位で変わる可能性もあります。あなたの事業ステージに合わせて、導入できるものから検討してみましょう。
8-1. 【基本中の基本】青色申告で最大65万円の控除を受ける
これはテクニックというより、事業所得者にとっての**「必須科目」です。第5章で詳しく解説した通り、青色申告(e-Tax利用)を行うだけで、利益(所得)から無条件で65万円**を差し引くことができます。
所得税率20%の方であれば、これだけで
65万円 × 20% = 13万円
住民税率10%(概算)も合わせれば、
65万円 × 10% = 6.5万円
合計で年間約19.5万円も納税額が減る計算になります。
会計ソフトを利用すれば、簿記の知識は不要です。まだ白色申告の方は、今すぐ青色申告への切り替えを検討しましょう。これほど簡単で効果の大きい節税策は他にありません。
8-2. 小規模企業共済に加入して所得控除を増やす
個人事業主の**「退職金制度」**とも言えるのが、この「小規模企業共済」です。
- 仕組み:毎月1,000円から7万円までの範囲で掛金を積み立てていき、将来事業を辞めた時や廃業した時に、積み立てたお金を退職金として受け取れる制度です。
- 節税効果:この制度の最大のメリットは、支払った掛金の全額が「所得控除」の対象になることです。
- 具体例:もし毎月最大の7万円を積み立てた場合、年間で**84万円(7万円 × 12ヶ月)が所得から控除されます。所得税率20%の方なら、これだけで約25.2万円(所得税16.8万円+住民税8.4万円)**も税金が安くなります。
将来の備えをしながら、現在の税金を大幅に圧縮できる、非常に強力な節税策です。利益が安定して出るようになったら、真っ先に検討すべき制度と言えるでしょう。
8-3. iDeCo(個人型確定拠出年金)で将来の備えと節税を両立
iDeCoは、自分で掛金を出して運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る**「私的年金制度」**です。これもまた、強力な節税効果を併せ持っています。
- 仕組み:毎月一定額(個人事業主は最大6.8万円/月)を積み立て、投資信託などで運用します。
- 節税効果:小規模企業共済と同様、支払った掛金の全額が「所得控除」になります。さらに、運用で得た利益(通常は約20%課税)も非課税になるという二重のメリットがあります。
- 注意点:原則として60歳まで引き出すことができないため、あくまで老後のための長期的な資産形成と位置づけ、無理のない範囲で始めることが重要です。
小規模企業共済とiDeCoは併用も可能です。両方を満額利用すれば、それだけで年間165.6万円もの所得控除枠を確保できます。
8-4. 利益が大きくなってきたら「法人化」を検討する
せどりの利益(所得)が年間800万円を超えてくると、個人事業主のままよりも、会社を設立して**「法人化」**した方が、トータルの税負担が軽くなる可能性があります。
- 法人化のメリット:
- 税率の違い: 個人の所得税が最大45%の累進課税なのに対し、法人税の税率は一定(約23%前後)です。一定の所得を超えると、法人の方が税率上有利になります。
- 経費の範囲が広がる: 自分への給与(役員報酬)を経費にできたり、生命保険料を経費にできたりと、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広がります。
- 社会的信用度の向上: 法人というだけで、取引や融資の際に信用度が高まります。
- 法人化のデメリット:
- 設立コストと維持コスト: 会社の設立に約20〜30万円の費用がかかるほか、赤字でも毎年最低約7万円の法人住民税が発生します。
- 事務負担の増加: 社会保険への加入義務や、より複雑な会計処理が必要になります。
法人化は大きなメリットがありますが、同時にコストと責任も増大します。税理士などの専門家と相談しながら、慎重に検討すべき選択肢です。
8-5. ふるさと納税を賢く活用する
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、自己負担額の2,000円を除いた全額が、翌年の**所得税・住民税から控除(還付)**され、さらに返礼品がもらえるという非常にお得な制度です。
- 節税との違い:厳密には「税金の前払い」であり、支払う税金の総額が減るわけではありません。しかし、自己負担2,000円で豪華な返礼品(寄付額の約30%相当)が手に入るため、実質的な節約効果は絶大です。
- ポイント:寄付できる上限額は、あなたの所得(利益)によって決まります。せどりで利益が上がれば上がるほど、ふるさと納税で寄付できる上限額も増えていきます。
各種ふるさと納税サイトで、あなたの所得に応じた上限額をシミュレーションできます。せっかく納める税金の一部を、お得な返礼品に変えられるこの制度を使わない手はありません。
9. まとめ|正しい税金の知識が、せどりを成功に導く
この記事では、せどりにおける税金の全体像を、基礎から応用まで網羅的に解説してきました。
確定申告が必要になる利益20万円・48万円の壁から始まり、節税の鍵となる経費の全リスト、そして手元にお金を残すための最強の武器である**「青色申告」とインボイス制度への対応策、さらには小規模企業共済やiDeCo**といった一歩進んだ節税テクニックまで、その全てを学びました。
もしかすると、あなたは「税金は利益を奪う面倒なもの」と考えていたかもしれません。しかし、ここまで読み進めた今、その考えは少し変わったのではないでしょうか。
そうです。税金とは、単なるコストではありません。それは**ビジネスというゲームの「公式ルールブック」**です。
このルールを知らないままでは、本来払う必要のないペナルティで利益を失ったり、使えるはずの優遇制度を見逃して損をしたりしてしまいます。一方で、ルールを正しく理解し、使いこなせば、税金はあなたの事業資金を守り、成長を加速させる**「最強の味方」**に変わるのです。
さあ、今日から始めるための、具体的なアクションプランを立てましょう。
- まずは記録から: 今すぐ、会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)の無料プランに登録し、銀行口座とクレジットカードを連携させてみましょう。全ての売上と経費の記録を始めることが、全ての第一歩です。
- 青色申告の準備を: あなたの利益が年間20万円を安定して超えそうなら、ためらわずに「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。その一枚の書類が、将来のあなたの手取りを大きく変えます。
- 専門家を頼る勇気を: もし事業が大きくなり、不安を感じたら、税理士への相談を検討してください。専門家への相談料は、あなたの時間と安心、そして大きな節税額をもたらす最高の投資です。
税金の知識を身につけたあなたは、ただ漠然と商品を売買していた過去の自分や、多くのライバルたちよりも、遥かに有利な地点に立っています。
もう税金のことで不安になる必要はありません。今日学んだ知識を武器に、自信を持ってせどりビジネスを拡大し、あなたの理想とする未来を実現してください。

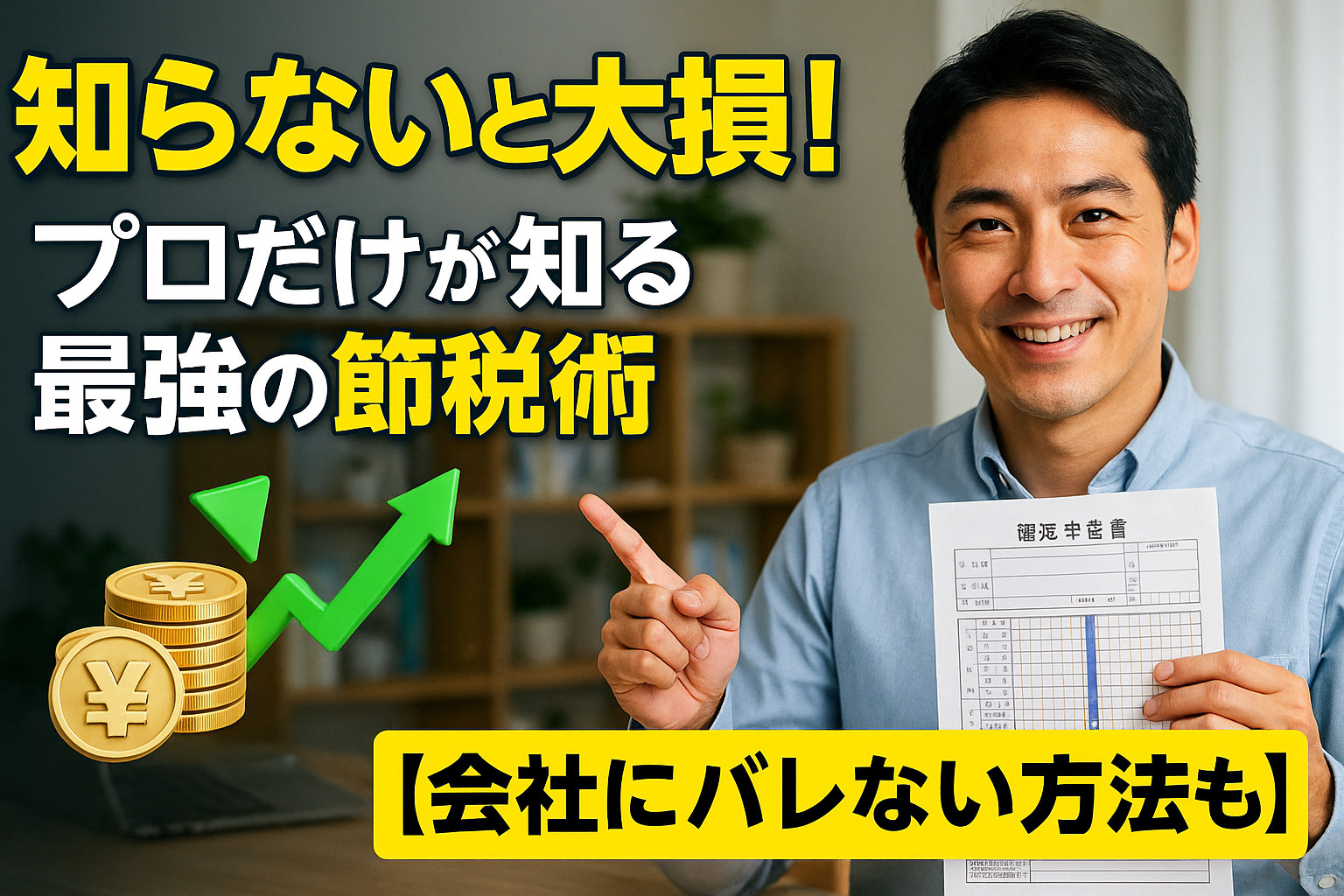

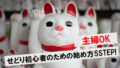
コメント