件名:「出品者様のAmazon出品アカウントに関する重要なお知らせ」
その一通の通知で、血の気が引くような感覚に襲われていませんか?
「真贋調査」― それは、Amazonセラーにとって「アカウント停止(アカスペ)」に直結する、最も恐ろしい言葉の一つです。焦って不適切な対応をしてしまえば、売上金は凍結され、最悪の場合、ビジネス生命そのものが絶たれてしまう可能性すらあります。
ですが、もし正しい知識と手順さえ知っていれば、この絶望的な状況を乗り越え、むしろ以前よりも強固なアカウントを築き上げることが可能だとしたら、どうでしょう。
想像してみてください。
真贋調査の恐怖に怯えることなく、自信を持って仕入れと販売に集中できる毎日を。Amazonという巨大なプラットフォームで、目先の利益ではなく、10年後も安定して稼ぎ続ける盤石な事業基盤を築き上げている、あなた自身の姿を。
この記事は、単なる付け焼き刃のテクニックを解説するものではありません。Amazonが求める「請求書」の具体的な条件から、審査官を納得させる「改善計画書」の書き方、そして二度と調査に怯えなくて済むための鉄壁の「予防策」まで、あなたのアカウントを守り抜くための**「教科書」**となる全ての知識を凝縮しました。
まず、深呼吸してください。そして、焦って返信ボタンを押すのは、絶対にやめてください。
この記事が、あなたのビジネス生命を守るための、最も確実な羅針盤となります。
はい、承知いたしました。
構成案に基づき、「はじめに」と「0.【緊急対応】」部分の本文を生成します。
はじめに:その通知は突然来る。アカウント停止(アカスペ)を回避するための全知識
スマートフォンの通知が鳴る。セラーセントラルのアプリを開くと、そこにはパフォーマンス通知を示す「赤い旗」。あるいは、メールボックスに届いた一件のメール。
件名:出品者様のAmazon出品アカウントに関する重要なお知らせ
この一文を目にした瞬間、多くのアクティブなセラーが同じ感覚に襲われます。頭が真っ白になり、心臓が早鐘を打つ、あの独特の感覚です。
そう、これがAmazonセラーにとって最も恐ろしい通知の一つ、「真贋調査」の始まりです。
この通知への対応を一つでも間違えれば、出品停止はもとより、売上金の長期留保、そして最悪の事態である**アカウント停止(通称:アカスペ)**へと、一直線に進んでしまいます。
しかし、絶望する必要はありません。
真贋調査は、正しい知識を持ち、正しい手順で、誠実に対応すれば、必ず乗り越えることができます。
この記事は、あなたがその絶体絶命のピンチを切り抜け、二度と同じ問題に悩まされることのない強固なビジネス基盤を築くための、**知識の全てを網羅した「教科書」**です。
0.【緊急対応】Amazonから真贋調査の通知が届いた人が、今すぐやるべき3つのこと
まず、落ち着いてください。パニックになり、感情的に行動することが、最も事態を悪化させます。
Amazonへの返信や、本格的な書類準備を始める前に、あなたのアカウントの運命を分ける、絶対に守るべき3つの鉄則があります。今すぐ、以下の行動を順番に実行してください。
0-1. 間違っても「謝罪文」や「言い訳」をすぐ送らない
通知を見て動揺し、「申し訳ありませんでした!」「購入者の勘違いです!」といった、感情的な謝罪や言い訳を反射的に返信してしまうのが、最も典型的な失敗パターンです。
Amazonのアカウントスペシャリストが求めているのは、あなたの反省の弁ではありません。彼らが要求しているのは、**真贋を証明するための「客観的な証拠書類」**と、**問題を解決するための「論理的な改善計画」**の2つだけです。
不十分な情報で中途半半端な返信を送ることは、あなたの立場を著しく不利にします。一度送った内容は取り消せません。まずはやるべきことを正確に把握するまで、絶対に返信ボタンを押さないでください。
0-2. 対象ASINの出品を即座に取り下げる(在庫返送・破棄)
Amazonに対して、「私たちはこの問題を真摯に受け止めています」という姿勢を示すための、最も重要で最初のアクションです。調査対象となったASIN(商品)の出品は、即座に停止してください。
- セラーセントラルにログインし、「在庫管理」画面を開きます。
- 通知に記載されている対象ASINを探し、出品ステータスを**「出品を終了」**に変更します。
- もしその商品がFBA倉庫にある場合は、間髪入れずに**「返送/所有権の放棄依頼」**を作成し、全ての在庫を手元に戻すか、破棄する手続きを行ってください。
この「迅速な出品取り下げ」という行動そのものが、後ほど提出する「改善計画書」において、「すでに行った是正措置」として強力な説得力を持ちます。
0-3. この記事を最後まで読み、必要な書類と情報を正確に把握する
焦りは最大の敵です。闇雲に行動しても、アカウント停止のリスクを高めるだけです。今あなたに必要なのは、敵(=Amazonの要求)を正確に知ることです。
この先この記事では、Amazonが認める**「請求書」の厳格な条件から、一発で審査を通過する「改善計画書」の具体的なフレームワーク**、そして二度と調査に怯えなくて済むための予防策まで、その全てを詳細に解説していきます。
正しい知識こそが、あなたのアカウントを守る唯一の武器となります。まずは腰を据えて、戦いの全体像を把握することから始めましょう。
1. そもそもAmazonの真贋調査とは?その種類と発生原因を理解する
緊急対応を終え、少しだけ冷静さを取り戻した今、まずは「敵」の正体を正確に理解することから始めましょう。
Amazonの真贋調査とは、あなたが販売している商品が「本物(正規品)」であり、「正規の流通経路」から仕入れたものであることを、Amazonに対して証明する手続きのことです。
Amazonがこの調査を非常に厳格に行う理由は、ただ一つ。Amazonというマーケットプレイス全体の「信頼」を守り、最高の顧客体験を維持するためです。
顧客が「Amazonで偽物が届いた」と感じる事態は、Amazonにとってブランドイメージを著しく損なう、絶対に避けたい最悪のシナリオです。そのため、少しでも疑わしい点があれば、「疑わしきは罰する」の姿勢で、出品者に対して100%の潔白証明を求めてきます。
この章では、あなたがAmazonの要求を正しく理解し、的確な対応ができるようになるために、調査の種類と主な発生原因を詳しく解説していきます。
1-1. なぜ調査が来る?3つの主なトリガー
真贋調査の通知は、決して無作為に送られてくるわけではありません。その背景には、必ず何らかの「きっかけ(トリガー)」が存在します。
1-1-1. 購入者からの「偽物・コピー品」という申告・低評価レビュー
これが、真贋調査が発生する最も一般的で直接的な原因です。
購入者が商品を返品する際、その理由として「偽物の疑い」を選択したり、セラー評価や商品レビューに**「偽物」「コピー品」「正規品ではない」「海賊版」**といったキーワードを書き込んだりすると、Amazonのシステムがそれを自動で検知し、調査が開始されます。
ここで重要なのは、購入者の申告が事実である必要はない、ということです。
例えば、
- 輸送中に商品の外箱が潰れてしまい、それを見た購入者が「新品なのに箱が汚い。偽物ではないか?」と疑った
- 商品の仕様がマイナーチェンジされ、手元に届いた商品のデザインがAmazonの商品ページと僅かに異なっていた
たとえ商品が100%本物であっても、購入者が少しでも「偽物かも?」と疑念を抱き、それを特定のキーワードでAmazonに伝えてしまえば、調査のトリガーとなり得るのです。
1-1-2. メーカー・ブランド権利者からの知的財産権の侵害申告
購入者からの申告よりも深刻で、対応が難しいのが、このメーカーやブランド権利者からの直接的な申し立てです。
多くの大手メーカーは、自社ブランドの価値を守るため、Amazonの**「ブランド登録(Amazon Brand Registry)」**という制度を利用して、プラットフォーム上の商品を常に監視しています。
そして、自社が認めた「正規販売代理店」以外で商品を販売しているセラーを見つけると、「知的財産権(商標権)の侵害」としてAmazonに申告します。この申告は極めて重く受け止められ、即座に真贋調査へと発展します。
このケースの恐ろしい点は、あなたが販売している商品が本物であっても、あなたが**「正規の販売ルート」から仕入れていない**というだけで、申告の対象になってしまうことです。
1-1-3. AmazonのAIによるランダム・抜き打ちチェック(出品数の急増など)
特定の申告があったわけではなく、Amazon自身のシステム(AI)が、あなたのアカウントの動向からリスクを検知し、調査を開始するパターンです。
- 出品数や売上の急増:新規セラーが、いきなり人気ブランドの商品を大量に出品したり、売上が急激に伸びたりすると、AIが「不審な動き」と判断することがあります。
- 高リスクカテゴリへの出品:偽物が多く流通している、あるいは過去にトラブルが多発したカテゴリ(例:高級ブランド品、有名メーカーのイヤホンなどの電子機器、サプリメント、DVDなど)へ出品すると、予防的なチェックが入りやすくなります。
- アカウントの健全性が低い:過去に別の規約違反を指摘されるなど、アカウント健全性指数が低下しているセラーは、より厳しい監視下に置かれます。
このAIによるチェックは、ある日突然、何の前触れもなく行われます。
1-2. 意外と知らない2つの調査パターン
「真贋調査」と一括りにされがちですが、実はその発生タイミングによって、大きく2つのパターンに分かれます。
1-2-1. 特定ASINの出品停止を伴う「出品者パフォーマンス通知」
これが、今回あなたに届いたであろう、最も典型的な**「事後調査」です。
何らかのトリガー(購入者の申告など)に基づき、問題が起きた後で**調査が入ります。セラーセントラルにパフォーマンス通知が届き、対象ASINは即座に出品停止。あなたは、その潔白を証明するために、書類の提出を求められます。
1-2-2. 出品許可申請時に求められる「事前調査」
一部の規制が厳しいブランドやカテゴリにおいて、そもそも商品を出品する前に、正規の仕入れルートを証明する書類の提出を求められるパターンです。これは、問題が起きるのを未然に防ぐための**「事前調査」**と言えます。
この出品許可申請をクリアできる仕入れルートを確保しているかどうかが、そもそも真贋調査に強いアカウントであるかどうかの、一つの指標となります。
2.【最重要】Amazonが要求する「請求書」の条件|レシートや領収書がNGな理由
真贋調査を突破できるかどうか。その運命の99%は、あなたが提出する**「書類の質」**で決まります。そして、ほとんどのセラーがここでつまずく最大の原因が、Amazonが要求する「請求書」と、あなたが「仕入れの証明書」だと思っている書類との、致命的な認識のズレです。
Amazonが確認したいのは、あなたが「その商品を購入した」という事実だけではありません。その商品が、**メーカーから卸売業者、そしてあなたへと続く、一点の曇りもない「正規のサプライチェーン(流通経路)」**を辿ってきたことの証明を求めているのです。
この章では、あなたのアカウントを守る生命線である「請求書」の条件を、Amazonの視点から徹底的に解説します。
2-1. これが通る請求書の条件!Amazonが求める7つの必須項目
Amazonに提出する請求書は、以下の7つの項目を**「すべて」「完全に」**満たしている必要があります。一つでも欠けていれば、その書類は無効と判断される可能性が非常に高くなります。ご自身の請求書と照らし合わせながら、厳しくチェックしてください。
(本記事の情報は2025年8月20日時点のものです)
- あなた(出品者)の名称と住所が記載されているか
- Amazonのセラーセントラルに登録している「正式名称または販売業者名」及び「住所」と、一言一句同じである必要があります。
- 仕入れ先の名称と住所、連絡先(電話番号・ウェブサイト)が記載されているか
- Amazonが、その仕入れ先が実在し、信頼できる業者であるかを追跡調査できるようにするためです。連絡先が記載されていない請求書は、それだけで信頼性が低いと見なされます。
- 発行日が過去365日以内であるか
- 直近の仕入れであることを証明する必要があります。
- 対象ASINと一致する商品名が明記されているか
- 型番やJANコードだけでなく、Amazonの商品ページと一致する具体的な商品名が記載されていることが理想です。
- 仕入れた数量が明記されているか(販売実績との整合性)
- 非常に重要なポイントです。Amazonが調査対象としている期間の販売数量以上の仕入れ数量が、請求書に記載されている必要があります。(例:直近1ヶ月で30個販売した商品の調査で、仕入れ数量5個の請求書を提出しても意味がありません)
- PDF、JPG、PNG、GIF形式であるか
- スキャンまたは写真でデータ化して提出します。スクリーンショットは原則として認められません。
- 改ざんの形跡がないか
- 言うまでもありませんが、デジタル・手書きを問わず、少しでも編集・改ざんした書類を提出することは最も重い規約違反です。絶対に行わないでください。
2-2. なぜ「小売店」のレシートは99%通らないのか?(ヤマダ電機、コストコ、ドン・キホーテ等)
多くの初心者が、「レシートも仕入れの証明になるはずだ」と考え、小売店のレシートを提出して調査に失敗します。Amazonが小売店のレシートを認めない理由は、サプライチェーンの観点から極めて明確です。
Amazonの定義では、メーカー → 卸売業者 → 小売店と商品が流通し、小売店は「最終消費者」へ商品を販売する場所と位置づけられています。
つまり、あなたがヤマダ電機やコストコ、ドン・キホーテといった小売店で商品を購入した場合、あなたはAmazonから「最終消費者」と見なされます。そこからAmazonで再販売する行為は、Amazonの定める「正規の流通経路」から外れた転売と判断されるのです。
レシートは、あなたが「消費者として商品を買った」証明にはなっても、「事業者として正規ルートから仕入れた」証明には決してならない、と覚えておきましょう。
2-3. ネットショップの「納品書」や「注文確認メール」は有効か?
原則として、ネットショップから発行される**「納品書」や、購入時に自動送信される「注文確認メール」のスクリーンショットは、証拠書類として認められません。**
- 納品書:あくまで「商品を納品した」という証明であり、取引の正式な証明書(請求書)とは見なされないため。
- 注文確認メール:誰でも簡単に編集・偽造が可能であると判断されるため。
唯一の例外は、そのネットショップがメーカー公式サイトや正規代理店であり、別途依頼することで**「2-1」の全項目を満たした正式な「請求書」または「領収書」**を発行してくれる場合です。その場合でも、メールのスクショではなく、正式に発行されたPDFなどの書類を提出する必要があります。
2-4. 請求書に価格を記載する必要はある?マスキング(黒塗り)はOK?
結論から言うと、価格情報のマスキング(黒塗り)はAmazonの公式ガイドラインで認められています。
Amazonが知りたいのは「商品の真贋」であり、あなたの仕入れ価格や利益率といった財務情報ではありません。これらはあなたの重要な経営情報ですので、開示する必要はありません。
【マスキング(黒塗り)する際の注意点】
- 仕入れ価格(単価、合計金額)以外の部分は絶対に消さないでください。
- 誤って発行日や商品名、数量といった必須項目まで消してしまうと、その請求書は無効となります。PDF編集ソフトや画像編集ソフトを使い、細心の注意を払って作業しましょう。
2-5. 信頼される仕入れ先の具体例(正規代理店、メーカー公式卸、大手卸売業者)
では、Amazonが「正規の流通経路」として認める、信頼性の高い仕入れ先とは具体的にどこなのでしょうか。
- メーカー
製造元であるメーカーから直接仕入れる方法です。最も安全で確実ですが、取引のハードルは高いです。
- 正規代理店(一次卸)
メーカーが公式に販売代理店として契約している、いわゆる「一次卸」です。メーカーのウェブサイトなどで代理店リストが公開されている場合があります。
- 大手総合卸売業者
特定のメーカーの代理店ではないものの、多数のメーカーと取引があり、事業者向けに商品を卸している企業です。BtoB向けの卸売サイト(例:スーパーデリバリー、**NETSEA(ネッシー)**など)もこれに含まれます。
これらの仕入れ先は、法人・個人事業主との取引を前提としているため、依頼すれば必ず**「2-1」の条件を満たした正式な請求書**を発行してくれます。
3.【例文テンプレート付】アカウントスペシャリストを納得させる「改善計画書」完全マニュアル
請求書が「過去」の潔白を証明する客観的な証拠だとすれば、この**「改善計画書(Plan of Action)」は、あなたの「未来」**における信頼性を示すための、主観的な約束です。
請求書だけ提出して、改善計画書が不十分な場合、審査を通過することはできません。この2つは、真贋調査を突破するための両輪なのです。
3-1. Amazonが知りたいのは「反省」ではなく「再発防止策」である
改善計画書で多くのセラーが犯す最大の過ち。それは、感情的な反省文や謝罪文を長々と書いてしまうことです。
Amazonのアカウントスペシャリスト(通称:アカスペ)は、毎日何百という改善計画書を処理しています。彼らが知りたいのは、あなたの反省の気持ちではありません。彼らが評価するのは、あなたが問題をビジネス上の課題として論理的に分析し、二度と同じ過ちを繰り返さないための、具体的で実行可能な「システム」を構築できるかどうか、という一点です。
「申し訳ありませんでした」は不要です。「今後はこのように改善します」という、未来志向の具体的な行動計画を示しましょう。
3-2. 改善計画書に盛り込むべき3つの必須項目
優れた改善計画書は、必ず以下の3つの要素で構成されています。このフレームワークに沿って書くことで、あなたの主張は驚くほど論理的で、説得力のあるものになります。
3-2-1. 根本原因:なぜ真贋を疑われる商品を出品してしまったのか
「なぜ、今回の問題が起きてしまったのか」その原因を分析し、正直に記載します。ここで重要なのは、購入者やメーカーのせいにするのではなく、自分自身の管理体制や認識の甘さに原因があったと認めることです。
3-2-2. 是正措置:通知を受け、すでに行った具体的な対応
Amazonから通知を受けた後、あなたが**「すでに行動したこと」**を具体的に報告します。これは、あなたが問題を真摯に受け止め、迅速に対応するセラーであることを示すための重要なアピールです。
3-2-3. 予防措置:今後、同様の問題を二度と起こさないための恒久的な仕組み
改善計画書の中で最も重要なパートです。今後、同様の問題を100%防ぐために、あなたはどのような**恒久的な仕組み(システム)**を導入するのか。精神論ではなく、誰がやっても同じ結果になるような、具体的な業務フローレベルでの改善策を提示する必要があります。
3-3.【コピペで使える】根本原因の書き方と例文
書き方のポイント: 自分の認識不足や確認不足が原因であったことを明確に認めます。
【例文テンプレート】
この度の問題が発生しました根本原因は、下記の点にあると認識しております。
- Amazonのポリシー、特に商品の真贋に関する規約についての私の理解が不十分でした。
- 出品前に、商品の仕入れ先がAmazonの定める正規流通経路であるかどうかの確認を怠っておりました。
- (購入者からの申告の場合)商品状態の確認が不十分なまま出品したことで、購入者様に「正規品ではない」との誤解とご不安を与えてしまいました。
3-4.【コピペで使える】是正措置の書き方と例文
書き方のポイント: 過去形で「〜しました」と、完了したアクションを具体的に記載します。
【例文テンプレート】
今回の通知を受け、以下の是正措置を直ちに実施いたしました。
- 真贋調査の対象となったASIN(ここにASINを記載)の出品を、直ちに停止いたしました。
- FBA倉庫に納品していた対象商品の在庫について、全て返送手続きを完了させました。
- 現在出品中の全商品について、仕入れ先が正規流通経路であることを証明する請求書が揃っているか、再度総点検を行いました。請求書が確認できない商品については、全て出品を停止いたしました。
3-5.【コピペで使える】予防措置の書き方と例文
書き方のポイント: 未来形で「〜します」と、具体的なアクションを箇条書きで複数提示します。誰が読んでも誤解の余地がないほど、具体的に書くことが重要です。
【例文テンプレート】
今後、同様の問題を再発させないため、以下の予防措置を導入し、恒久的に運用することをお約束いたします。
1. 仕入れに関する改善策:
- 仕入れ先を、メーカーもしくはAmazonが認める正規代理店、正規卸売業者のみに限定します。小売店や、正規ルートであることが確認できないネットショップからの仕入れは一切行いません。
- 新規取引先と契約する際は、必ず事前に取引契約書を締結し、Amazonの定める全ての要件を満たした請求書が発行可能であることを確認した上で、取引を開始します。
2. 出品・検品に関する改善策:
- 商品の出品前に、必ず請求書と商品を照合し、商品名、型番、数量に相違がないかを確認するダブルチェック体制を導入します。
- 商品にメーカー保証書やシリアルナンバーがある場合、それらが同梱されていることを必ず確認します。外箱の損傷や付属品の欠品がないか、詳細な検品チェックリストを作成し、それに従って検品作業を行います。
3. 在庫管理に関する改善策:
- 全ての商品について、ASINと仕入れ日、仕入れ先、対応する請求書番号を紐付けた在庫管理表(Excel)を作成し、いつでも追跡可能な状態を維持します。
3-6. やってはいけないNGな書き方ワースト3
- 購入者やメーカーを批判する
「購入者の勘違いです」「メーカーの不当な申告です」といった他責の姿勢は、Amazonに「このセラーは反省していない」と判断され、一発でアウトです。
- 感情的な謝罪や長文の反省文
「深く反省しております」「二度とこのようなことは…」といった精神論は評価されません。淡々と、論理的に、具体的な改善策だけを書きましょう。
- 抽象的な改善策
「今後は気をつけます」「もっとしっかり確認します」「従業員教育を徹底します」といった、具体性のない言葉は無意味です。「誰が、いつ、何を、どのように」行うのかを明確に記述しなければ、改善計画とは見なされません。
4. そもそも真贋調査を二度と受けないための「予防策」5選
改善計画書を提出し、無事にアカウントが復活したとしても、それはあくまで対症療法にすぎません。本当の勝利は、真贋調査の脅威に怯えることのない、強固でクリーンな事業体制を構築することにあります。
この章では、あなたがAmazonというプラットフォームで長期的に、そして安心してビジネスを続けるための、守りであり、同時に攻めでもある5つの予防策を具体的に解説します。
これから紹介するのは、あなたのアカウントを守る「保険」であり、盤石なビジネスの「土台」となる、すべてのセラーが実践すべき行動指針です。
4-1. 仕入れ先を「正規流通経路」に限定する(卸売業者・正規代理店リストの作り方)
これが最も本質的で、最も強力な予防策です。あなたの仕入れが100%クリーンであれば、どんな調査が来ても、あなたは常に完璧な証明書類(請求書)を提示できます。
小売店からの仕入れ(店舗せどり)は、どんなに利益が出ようとも、常に真贋調査のリスクと隣り合わせです。ビジネスを本気で守りたいなら、仕入れ先を以下の「正規流通経路」へと完全にシフトさせましょう。
- 信頼できる仕入れ先の探し方
- メーカーの公式サイトを確認する:多くのメーカーは、公式サイトに「法人のお客様へ」「お取引について」といった窓口を設けています。また、「正規代理店一覧」を公開している場合もあります。
- 業界の見本市・展示会に足を運ぶ:「東京おもちゃショー」や「ギフト・ショー」といった業界のイベントは、メーカーや一次卸の担当者と直接繋がり、取引のきっかけを作る絶好の機会です。
- BtoB卸売サイトに登録する:**「スーパーデリバリー」や「NETSEA(ネッシー)」**といった、事業者向けの卸売サイトには、信頼できる業者が多数登録しています。まずはここから取引を始め、実績を積むのが現実的です。
これらの正規ルートから仕入れた実績を積み重ね、**あなただけの「取引可能卸売業者リスト」**をExcelなどで作成・管理していくこと。それこそが、あなたのアカウントを守る最強の資産となります。
4-2. メーカーの保証書やシリアルナンバーの管理を徹底する
請求書と並行して、個々の商品の真正性を証明する**「物的証拠」**の管理も徹底しましょう。
- 保証書:特に家電製品などで、外箱に店舗印が押された保証書が添付されている場合、それが正規販売店からの流通品であることの間接的な証明になります。顧客に送付する前に、保証書が適切に扱われているかを確認する一手間が重要です。
- シリアルナンバー:高価格帯の電子機器などを扱う場合、発送する商品のシリアルナンバーを控え、注文情報と紐づけて管理することを強く推奨します。これは、悪意のある購入者が商品をすり替えて返品してくる、といった詐欺行為への強力な対抗策にもなります。
これらの丁寧な管理体制は、万が一の際の二次的な証拠となるだけでなく、あなたのビジネスに対するプロ意識を高めることにも繋がります。
4-3. 出品時に危険なブランド・商品を避ける(セラースプライト等の外部ツール活用法)
戦う前から「負け戦」だとわかっている市場に、あえて参入する必要はありません。特に、メーカー自身がAmazonでの販売に力を入れていたり、厳格な販売代理店制度を敷いていたりする**「高リスクブランド」**の出品は、初心者のうちは避けるのが賢明です。
- 高リスクブランドの見分け方
- 大手有名メーカー:SONY、Panasonic、Apple、有名化粧品ブランドなどは、常に第三者セラーを監視しています。
- Amazon自身が出品している:Amazon本体が販売している商品ページに相乗り出品するのは、非常に高いリスクを伴います。
- 外部ツールの活用:**セラースプライト(SellerSprite)**などのサードパーティ製ツールを使えば、ASINを入力するだけで、その商品に「出品制限」がかかっているか、あるいはブランド自体が監視を強めているかを、ある程度事前に察知することが可能です。
利益が出るからといって安易に飛びつくのではなく、その裏にある「リスク」をデータに基づいて判断する冷静さを持ちましょう。
4-4. 高リスクな出品形態を避ける(並行輸入品、中古品のコンディション説明など)
何を売るかだけでなく、「どのように売るか」も重要です。以下の出品形態は、真贋調査のトリガーとなりやすいため、特に注意が必要です。
- 並行輸入品:規約上は認められていますが、真贋調査が来た際の証明のハードルが非常に高くなります(海外の正規ルートを証明する必要があるため)。明確な証明書類が揃えられない限り、安易に手を出すべきではありません。
- 中古品:「ほぼ新品」や「非常に良い」といったコンディションで出品した商品が、購入者の期待値を下回った場合、「思っていたより状態が悪い。偽物かもしれない」というクレームに繋がりやすくなります。対策は**「コンディションを一つ下げて出品する」**こと。「非常に良い」と思っても「良い」で出品すれば、購入者の満足度は上がり、クレームのリスクは激減します。
常に購入者の期待値を少しだけ上回る。この「アンダープロミス・オーバーデリバー」の精神が、あなたのアカウントを守ります。
4-5. 購入者からの問い合わせやクレームには24時間以内に神対応を徹底する
真贋調査の多くは、元をたどれば購入者の些細な不満から始まっています。顧客がAmazonに直接申告する前に、あなたの段階でその不満を解消してしまえば、調査の芽を摘むことができるのです。
- 神対応の3原則
- 24時間以内の迅速な返信:Amazonがパフォーマンス指標として重視しているだけでなく、顧客の不満が大きくなるのを防ぎます。
- 共感と謝罪:たとえあなたに非がないと思っても、まずは「ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」と、相手の感情に寄り添う一文から始めましょう。
- 議論より返金:揉めるだけ時間と労力の無駄です。顧客が納得しない場合は、議論せずに「着払いでご返品いただければ、全額返金させていただきます」と、迅速な返金対応を提案しましょう。数千円の損失でアカウントを守れるなら、それは必要経費です。
最高の顧客対応は、最高の真贋調査予防策です。
5.【ケース別】Amazon真贋調査に関するQ&A
真贋調査の基本的な流れと対策は理解できても、個々の状況によっては「こんな時はどうすれば?」という特殊な疑問や不安が湧いてくるものです。
この章では、多くのセラーが直面しがちな、より具体的なケースに関する質問にQ&A形式で回答し、あなたの最後の疑問を解消します。
5-1. Q. 請求書がどうしても提出できない場合はどうすればいい?
A. 非常に厳しい状況ですが、可能性はゼロではありません。正直に非を認め、完璧な改善計画書を提出することに全力を注いでください。
小売店からの仕入れなどで、Amazonの要求する請求書が物理的に提出不可能な場合、それは絶望的な状況です。しかし、アカウントを守るためにできることは残っています。
- 正直に事実を伝える
改善計画書の「根本原因」の項目で、「Amazon様の求める正規流通経路の認識が不足しており、小売店から仕入れた商品を販売しておりました。そのため、要件を満たす請求書を提出することができません」と、正直に、そして簡潔に事実を認めます。嘘や言い訳は絶対にいけません。
- 改善計画書に全てを賭ける
書類での証明ができない以上、あなたの未来の行動計画、すなわち**「予防措置」の項目が、アカウントの運命を分ける唯一の生命線**となります。二度とこのような過ちを犯さないために、どれだけ具体的で、実行可能で、恒久的なシステムを構築したかを、第3章で解説した以上に詳細かつ情熱的に記述してください。
この対応で、対象ASINの販売再開はほぼ不可能ですが、アカウント本体の停止(アカスペ)を回避できる可能性は残されています。「もう書類がないからダメだ」と諦めるのではなく、未来の改善計画でAmazonの信頼を取り戻すことに集中しましょう。
5-2. Q. 改善計画書を提出したが、Amazonから返信がない場合は?
A. 絶対にやってはいけないのは「催促の連絡」です。ひたすら辛抱強く待ってください。
改善計画書を提出すると、「ちゃんと届いただろうか」「審査はどうなっているだろうか」と不安になる気持ちは痛いほど分かります。しかし、ここで焦りは禁物です。
Amazonの審査には、数日で終わるケースもあれば、数週間、場合によっては1ヶ月以上かかることもあります。審査中に「どうなっていますか?」と何度も問い合わせたり、同じ書類を再提出したりすると、あなたのケースが審査キューの最後尾に戻されてしまい、さらに時間がかかる原因になると言われています。
Amazonから追加の書類提出を求められない限り、あなたは**「静観」**を貫いてください。その間も、改善計画書に書いた予防措置を実際に自分のビジネスに導入し、次のアクションに備えましょう。
5-3. Q. 中古品(古物)の真贋調査が来た場合の対処法は?
A. 請求書に代わる「正規の仕入れ」を証明する書類として、「古物台帳の写し」と「古物商許可証」を提出します。
中古品(古物)であっても、真贋調査の目的は同じです。あなたがその商品を、盗品などではなく、合法的に入手したことを証明する必要があります。
- 提出すべき書類
- 古物台帳の写し:これが請求書の代わりとなる最重要書類です。古物営業法で記録が義務付けられている「いつ、誰から、何を」仕入れたかの記録(台帳)から、対象商品の項目をスキャンまたは撮影して提出します。
- 古物商許可証の写し:あなたが、公安委員会の許可を得て営業している正規の古物商であることを証明します。
- その他:仕入れた商品の写真や、元の所有者から受け取った際のレシートや保証書があれば、補足資料として提出します。
改善計画書には、古物営業法を遵守し、正規の査定・買取プロセスを経て商品を仕入れていることを明記しましょう。
5-4. Q. 並行輸入品で真贋調査が来た場合の注意点は?
A. 日本国内ではなく、「海外の正規流通経路」を証明する必要があります。難易度は非常に高いです。
並行輸入品の真贋調査は、最もクリアするのが難しい案件の一つです。Amazonは、その商品が製造された海外の国において、あなたが正規のルートから仕入れたことを証明するよう求めてきます。
- 必要となる書類の例
- 海外のメーカーや正規代理店が発行した請求書(Invoice)
- 輸出入の記録がわかる通関書類
- メーカーが発行した正規品証明書(Certificate of Authenticity)
これらの書類を揃え、必要であれば日本語訳を添付して提出する必要があります。単に「商品は本物です」と主張するだけでは全く通用しません。海外のサプライチェーンまで完璧に証明できない限り、並行輸入品の扱いは極めて高いリスクを伴うと認識してください。
5-5. Q. 提出を無視し続けるとどうなる?(アカウント停止、売上金留保)
A. 最もやってはいけない最悪の選択です。ほぼ100%、アカウント停止と売上金の長期留保に至ります。
真贋調査の通知は、絶対に無視してはいけません。指定された期限内に何の応答もしなかった場合、Amazonは「このセラーは商品の真贋を証明できない、悪質なセラーである」と機械的に判断します。
その結果として、
- アカウントの永久停止(アカスペ)
- 売上金の90日以上の長期留保(凍結)
- FBA在庫の強制破棄
といった、ビジネスの存続が不可能になる、最も重いペナルティが課せられます。問題から目を背けても、事態は悪化の一途を辿るだけです。たとえ提出できる書類がなくても、必ず誠実に対応の意思を見せることが重要です。
5-6. Q. 真贋調査に強い専門家や代行業者に相談すべき?
A. アカウントの存続が最優先であれば、有力な選択肢です。ただし、業者の見極めは慎重に行ってください。
真贋調査は専門性が高く、一回のミスが命取りになるため、経験豊富な専門家のサポートを受けることには大きなメリットがあります。
- メリット:過去の膨大な事例に基づき、Amazonが納得する書類の形式や、改善計画書の「通る書き方」を熟知しているため、自力で対応するよりも通過率が格段に上がります。
- 注意点:一方で、「100%解決します」と無責任な保証を謳う業者や、法外な料金を請求する悪質な業者も存在します。
- 業者の選び方:依頼する際は、必ず事前に無料相談を利用し、①具体的な実績や事例を提示してくれるか、②あなたの状況をしっかりヒアリングしてくれるか、③明確な料金体系とサービス範囲を説明してくれるか、といった点を確認し、信頼できる相手かを見極めましょう。
あなたのビジネスにとって、数万円〜数十万円の投資でアカウントを守れるのであれば、それは決して高い費用ではないはずです。
まとめ|最高の防御は「正規ルートでの仕入れ」と「完璧な書類管理」にあり
Amazonから届く、あの心臓が凍りつくような「真贋調査」の通知。この記事では、その絶望的な状況からあなたのアカウントを守り抜き、ビジネスを再建するための具体的な知識と手順を、段階を追って徹底的に解説してきました。
緊急時に取るべき最初の一歩から、Amazonを納得させる「請求書」の厳格な条件、一発で審査を通過するための「改善計画書」のフレームワーク、そして特殊なケースに対応するためのQ&Aまで。あなたは今、真贋調査という「敵」と戦うための、ほぼ全ての武器を手に入れたはずです。
最後に、これら全てのテクニックの根幹をなす、最も重要で、そして最もシンプルな二つの原則を、改めて心に刻んでください。
- 最高の攻撃(=成長戦略)は、「正規ルートでの仕入れ」であること
結局のところ、真贋調査の問題はすべて「仕入れ」に起因します。小売店からの仕入れ(せどり・転売)は、常にリスクと隣り合わせです。
しかし、あなたがメーカーや正規卸売業者との取引へとビジネスモデルを昇華させた瞬間、あなたはAmazonの規約を遵守する、胸を張れる「事業者」となります。正規ルートからの仕入れは、調査を恐れる必要がなくなるだけでなく、安定した在庫確保とビジネスの拡大にも繋がる、最高の成長戦略なのです。
- 最高の防御(=リスク管理)は、「完璧な書類管理」であること
どれだけクリーンな仕入れを心がけていても、AmazonのAIや購入者の誤解によって、調査の可能性をゼロにすることはできません。その万が一の際にあなたを守るのが、日々の「完璧な書類管理」です。
いつ、どの商品を、どの業者から、いくつ仕入れたのか。それを示す請求書が、いつでも5秒以内に取り出せる状態にあること。この盤石な守りがあって初めて、あなたは安心してアクセルを踏み込むことができるのです。
真贋調査は、Amazonセラーにとって最大の脅威の一つです。しかし、それは同時に、あなたのビジネスが「その場しのぎの転売」から**「長期的に存続可能な、本物の物販事業」**へと脱皮するための、厳しいながらも価値ある試練でもあります。
この記事で得た知識を羅針盤とし、どうか臆することなく、より強く、よりクリーンなビジネスを構築してください。あなたのAmazonでの成功を、心から願っています。

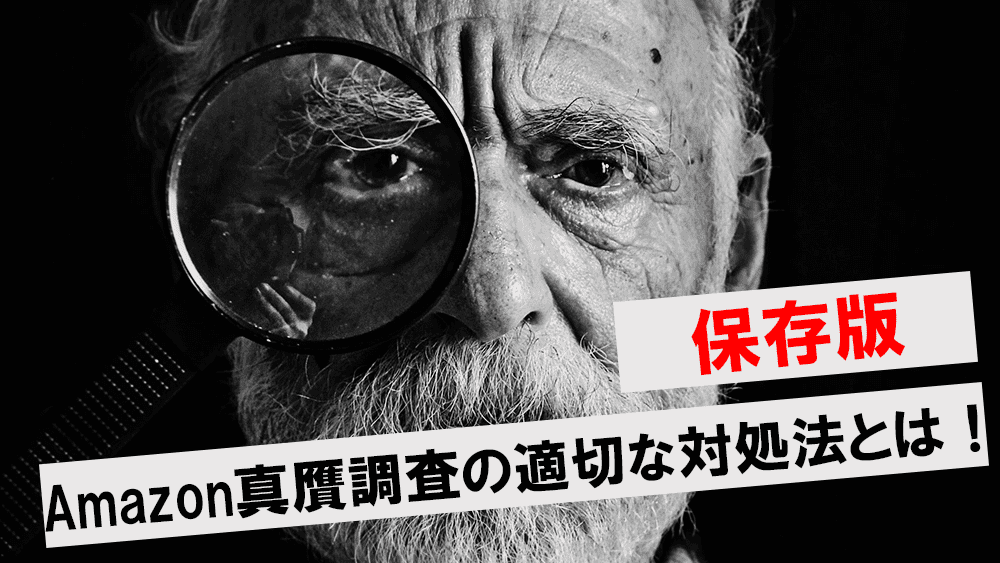
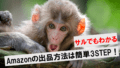
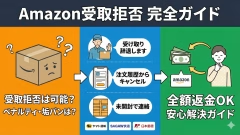
コメント