「歩くだけで稼げる」「これからの時代はHealthFiだ」──そんな甘い言葉で、あなたの友人やSNSの知人がinPersona(Vyvo)への参加を誘ってきたかもしれません。
しかし、あなたの心に生まれた**「…それって本当に大丈夫?マルチじゃないの?」**という直感。まずは、その賢明な疑いを、ご自身で褒めてあげてください。
この記事は、inPersonaを推奨も否定もしません。ただ、勧誘者が決して語らない**「不都合なデータ」と「ビジネスモデルのカラクリ」**を白日の下に晒し、あなた自身が「絶対的な自信を持って、YESかNOかを判断する」ための、最強の”調査報告書”です。
あなたの勘は正しいのか、それともただの思い過ごしか。そして、もし大切な友人を止めるべきなら、あなたは何を根拠に説得するのか。
その答えの全てが、ここにあります。
- 1.【結論】inPersona(Vyvo)は詐欺か?当サイトの最終的な見解
- 2. そもそもinPersona(Vyvo)とは何か?公式が説明するビジネスモデル
- 3. なぜinPersona(Vyvo)は「怪しい」と言われるのか?5つの重大な疑惑
- 4.【法的検証】inPersona(Vyvo)は「ねずみ講(無限連鎖講)」にあたるのか?
- 5. inPersona(Vyvo)のリアルな評判と口コミ
- 6. もしあなたが勧誘されたら。その場で使える質問リストと断り方
- 7. まとめ:全てのデータを踏まえて、あなたが今すぐ取るべき行動
1.【結論】inPersona(Vyvo)は詐欺か?当サイトの最終的な見解
「怪しい」「マルチじゃないの?」「本当に稼げるの?」──友人や知人からinPersona(Vyvo)の話を聞いたあなたが、そうした疑念を抱くのは至極当然のことです。
この章では、記事全体の結論を最初に提示します。曖昧な表現は一切使いません。あなたが最も知りたいであろう問いに、単刀直入にお答えします。
1-1. 結論:法律上の「ねずみ講」とは断定できないが、極めてハイリスクな「MLM(マルチ商法)」モデルである
まず、当サイトの最終的な見解を申し上げます。
現在の日本の法律において、inPersona(Vyvo)のビジネスモデルを、製品やサービスが全く介在しない**「ねずみ講(無限連鎖講)」と断定することは困難**です。なぜなら、「スマートウォッチ」と「データNFT」という、形のある「商品」が存在するからです。
しかし、そのビジネスの仕組みや報酬体系は、友人や知人を勧誘し、組織を拡大していくことで収益が生まれる**「MLM(マルチレベルマーケティング/連鎖販売取引)」**の典型的な特徴を色濃く持っています。
そして、数あるMLMの中でも、初期費用が高額であること、報酬における勧誘の比重が大きいと見られること、価値が不安定な暗号資産が関わることなどから、極めてハイリスクな投機的案件であると結論付けます。
1-2. なぜ「怪しい」「やばい」という声が絶えないのか?問題の本質
では、なぜこれほどまでに「怪しい」という声が上がるのでしょうか。
その問題の本質は、**「本当に価値があるのは、製品(スマートウォッチ)なのか、それとも他人を勧誘する権利なのか」**という点が、極めて曖昧になっていることにあります。
もし、多くの参加者が製品そのものの価値よりも、「誰かを勧誘すれば儲かる」という期待感から高額な初期費用を支払っているのだとすれば、その構造は実質的に、新規参入者のお金が既存の参加者に流れるだけの、持続可能性の低いマネーゲームと化してしまいます。
1-3. この記事の目的:あなたを勧誘する人が“絶対に言わない”不都合な真実を全てデータで示すこと
この記事の目的は、inPersona(Vyvo)を一方的に推奨したり、感情的に否定したりすることではありません。
私たちの目的はただ一つ。あなたを勧誘する人が、熱意を込めて語る「夢」や「理想」の裏側にある、彼らが“絶対に言わない”不都合な真実を、客観的なデータに基づいて、全て白日の下に晒すことです。
- そのスマートウォッチの性能は、本当に価格に見合っているのか?
- 報酬の源泉となる「VSCトークン」の現在の価値と、将来性は?
- ビジネスモデルは、法律的にどこがグレーで、どこがセーフなのか?
これらの情報を全て提供し、最終的な判断をあなた自身に下してもらう。それが、この記事の役割です。
1-4. 参加を検討する前に、あなた自身に問うべき5つの最終チェックリスト
本編に進む前に、まずはあなた自身の心に、以下の5つの質問を投げかけてみてください。
- もし**「誰一人勧誘できなくても、このスマートウォッチとNFTに数十万円を払う価値がある」**と心から思えますか?
- あなたが投じようとしている資金は、明日**ゼロになっても、あなたの生活や将来設計に一切影響のない「完全な余裕資金」**ですか?
- このビジネスモデルの仕組みとリスクを、あなたの大切な家族や親友に、自信を持って淀みなく説明できますか?
- 「歩くだけで稼げる」という言葉の裏にある、VSCトークンの価格暴落リスクも受け入れる覚悟はありますか?
- もし友人や家族から「それって、ねずみ講じゃないの?」と問われた時、明確な根拠をもって、冷静に反論できますか?
もし、一つでも「いいえ」や「自信がない」という答えがあったなら、この先を注意深く読み進めることを強くお勧めします。
2. そもそもinPersona(Vyvo)とは何か?公式が説明するビジネスモデル
inPersona(Vyvo)が「怪しい」かどうかを判断する前に、まずは彼らが「自分たちは何者で、何をしようとしているのか」をどう説明しているのか、正確に理解する必要があります。
この章では、公式の発表や資料に基づき、彼らが掲げるビジネスの全体像を、一切の評価を挟まずに中立的な立場で解説します。
2-1. 表向きの顔:「Web3 × HealthFi」で健康データを収益化する未来のプロジェクト
inPersona(Vyvo)が公式に掲げるビジョンは、**「Web3とHealthFiの技術を融合させ、個人が自身の健康データを管理・収益化できる、新しい経済圏を創出する」**という壮大なものです。
ここで登場する2つのキーワードを簡単に解説します。
- Web3(ウェブスリー):これは、GAFA(Google, Appleなど)のような巨大IT企業に独占されていたインターネットの世界を、ブロックチェーン技術によって、より分散化し、個人の手に取り戻そうという次世代の概念です。**「自分のデータは、自分で所有し、自分で価値を決める」**というのがWeb3の核となる思想です。
- HealthFi(ヘルスファイ):これは「Health(健康)」と「Finance(金融)」を組み合わせた造語です。歩いたり、運動したり、健康的な生活習慣を送ることで、暗号資産などの経済的なリターンが得られる仕組みを指します。「Move to Earn(歩いて稼ぐ)」の、より広範で進化した概念とされています。
つまり、inPersona(Vyvo)は、**「これまで企業にタダで提供していたあなたの貴重な健康データを、あなた自身の資産に変え、健康になるほど豊かになれる未来を作る」**というのが、公式が語るプロジェクトの「表向きの顔」なのです。
2-2. 登場する3つの要素:「Vyvoスマートウォッチ」「データNFT」「VSCトークン」の役割
この壮大なビジョンを実現するために、inPersona(Vyvo)は主に3つの要素を用意しています。それぞれの役割は以下の通りです。
- Vyvoスマートウォッチ(データ収集デバイス):心拍数、睡眠の質、歩数といったあなたの生体データを24時間収集するためのセンサーです。このウォッチを身につけることが、全ての活動の起点となります。
- データNFT(データの所有権):収集されたあなたの健康データを、ブロックチェーン上で**「あなただけの資産」として証明するための、デジタルな権利証**のようなものです。この「データNFT」を所有することで初めて、あなたは自身の健康データから報酬を受け取る権利を得ます。NFTには複数のレベルがあり、そのレベルに応じて報酬の量が変動するとされています。
- VSCトークン(報酬となる暗号資産):あなたが提供した健康データの対価として、報酬(リワード)として支払われる、この経済圏独自の暗号資産です。獲得したVSCトークンは、将来的には様々な製品やサービスと交換できるようになる、というのが公式の構想です。
2-3.「歩くだけで稼げる」仕組みの解説(ウェアラブルマイニング)
では、上記の3つの要素は、どのように連動して「歩くだけで稼げる」仕組みを成り立たせているのでしょうか。その流れは以下の通りです。
- 【収集】 あなたが**「Vyvoスマートウォッチ」**を腕につけて、日常生活を送ります。
- 【所有】 ウォッチが収集したあなたの健康データは、あなたが所有する**「データNFT」**に、個人が特定されない形で匿名化されて紐付けられます。
- 【報酬】 データを提供した対価として、inPersonaのシステムから、あなたのウォレットに毎日**「VSCトークン」**が支払われます。
この一連の流れを、inPersona(Vyvo)は**「ウェアラブルマイニング」**と呼んでいます。これは、ウェアラブルデバイス(スマートウォッチ)を身につけることで、暗号資産(VSCトークン)を採掘(マイニング)する、という意味です。
これが、inPersona(Vyvo)が公式に語る、美しく革新的なビジネスモデルの全貌です。
しかし、多くの人が強い疑念を抱くのは、このストーリーの裏側にある、具体的な費用、そして「誰が、どのようにして儲かるのか」という報酬体系の詳細です。
次の章では、いよいよ本題である、なぜこのモデルが「怪しい」「マルチではないか」と言われるのか、その核心に迫っていきます。
3. なぜinPersona(Vyvo)は「怪しい」と言われるのか?5つの重大な疑惑
前の章で解説した公式のビジネスモデルは、一見すると革新的で、夢のあるプロジェクトに聞こえるかもしれません。しかし、その具体的な仕組みや費用、そして報酬体系を詳しく見ていくと、多くの人が強い疑念を抱くであろう「5つの重大な疑惑」が浮かび上がってきます。
この章では、勧誘者が決して詳しく語りたがらない、このビジネスの核心に迫ります。
3-1. 疑惑1:ビジネスモデルが「MLM(マルチ商法)」そのものではないか?
「これはネットワークビジネスじゃない、Web3の最新プロジェクトだ」と説明されたかもしれません。しかし、その報酬体系を分析すると、典型的なMLM(マルチレベルマーケティング)の特徴が随所に見られます。
3-1-1. 報酬体系の分析:製品販売の利益より、紹介者(リファラル)勧誘による報酬がメインではないか
inPersonaの報酬プランは非常に複雑ですが、その核心は、自分が紹介した人(ダウンライン)が製品(NFTやウォッチ)を購入したり、さらに新しい人を紹介したりすることで、あなたに報酬が入るという点にあります。
製品そのものを販売して得られる利益よりも、**「他人を勧誘すること」**が収益の大きな柱となっているように設計されています。もしビジネスの主目的が「製品を広めること」ではなく「会員を増やすこと」になっているのであれば、それはMLMと酷似していると言わざるを得ません。
3-1-2. アップライン・ダウンラインという組織構造とバイナリーボーナスの仕組み
inPersonaの報酬体系には、「バイナリーボーナス」というMLMで頻繁に用いられる仕組みが採用されています。
これは、自分を頂点として、左右2つの系列(レッグ)にダウンラインを配置していく組織構造です。そして、左右のレッグの売上(ポイント)が一定の基準に達すると、ボーナスが支払われます。この仕組みでは、個人の努力だけでなく、自分の上位の紹介者(アップライン)の配置戦略によっても収入が変動するため、組織的な勧誘活動が活発化しやすい傾向があります。
3-2. 疑惑2:初期費用が異常に高額ではないか?
「歩くだけで稼げる」という手軽なイメージとは裏腹に、本格的に参加するための初期費用は、決して安価ではありません。
3-2-1.「データNFT」の価格設定(0〜,550)と、その価値の客観的根拠
報酬を得る権利である「データNFT」は、複数のレベルに分かれており、その価格は**1,550(約24万円)**にも及びます。
ここで重大な疑問が生じます。このNFTの価格は、一体何を根拠に設定されているのでしょうか?
一般的なNFTのように、著名なアーティストの作品であったり、人気ゲームの希少アイテムであったりするわけではありません。その価値は、inPersonaのシステム内でのみ通用するものであり、外部の市場で客観的に評価されたものではないのです。
3-2-2. スマートウォッチ本体(0〜)とのセット購入が前提となっている点
さらに、データNFTだけでは報酬は得られません。データを収集するための**Vyvoスマートウォッチ($200〜$400程度)**を別途購入する必要があります。つまり、本格的に参加しようとすれば、NFTとウォッチを合わせて、数十万円単位の初期投資が必要になる計算です。
3-3. 疑惑3:暗号資産「VSCトークン」の価値は本物か?
「歩くだけで稼げる」という言葉の「稼げる」部分を担うのが、報酬として支払われるVSCトークンです。しかし、このトークンの価値には、いくつかの重大な懸念点があります。
3-3-1. 2025年最新のVSCトークンの価格推移チャートと、その客観的評価
VSCトークンの価格は、2024年に一時的な高値をつけた後、2025年に入ってからは長期的な下落トレンドにあります。CoinGeckoなどの暗号資産情報サイトで確認すると、直近1年間で価格は約80%下落しており、多くの参加者が高値掴みとなり、大きな含み損を抱えている可能性が示唆されます。
3-3-2. 主要な暗号資産取引所(Coinbase, Binance等)に上場していない事実
暗号資産の信頼性を示す一つの指標が、世界的に有名な大手取引所への上場です。大手取引所は、上場させる銘柄に対して厳格な審査を行います。
2025年7月現在、VSCトークンは、**Binance、Coinbase、Krakenといった、世界トップクラスの取引所には一切上場していません。**流動性が低く、一部の中小取引所でしか売買できないという事実は、その資産価値と信頼性に対する大きな懸念材料です。
3-3-3. トークンの価格が、新規参入者の資金流入に依存している可能性はないか?
VSCトークンを欲しがる「買い圧力」は、どこから生まれるのでしょうか?
もし、その需要のほとんどが「これからinPersonaを始める新規参入者が、報酬を得るためにトークンを必要とするから」という理由だけで成り立っているとすれば、それは極めて危険な状態です。
新規参入者がいる間は価格が維持されるかもしれませんが、勧誘が頭打ちになった瞬間、買い圧力が消滅し、トークン価格が暴落するという、典型的なポンジ・スキーム(自転車操業)に陥るリスクを内包しています。
3-4. 疑惑4:製品(スマートウォッチ)の性能は価格に見合っているか?
MLMが合法的なビジネスとして成立するためには、「製品の価値」が価格に見合っていることが大前提です。
3-4-1. Vyvo Watch LITE SE vs Apple Watch SE vs Fitbitのスペック比較
Vyvo Watch LITE SE($249)と、同価格帯のメジャーな製品であるApple Watch SE($249〜)やFitbit Sense 2($299)のスペックを比較すると、ディスプレイの解像度、搭載されているセンサーの種類、アプリ連携のスムーズさなど、多くの点でVyvo Watchが見劣りするという指摘が少なくありません。
3-4-2. Amazon等での一般販売が無く、性能を客観的に評価しづらい点
最大の問題は、VyvoのスマートウォッチがAmazonや家電量販店といった一般市場で販売されていないことです。これにより、私たちは第三者による公平なレビューや、他の製品との客観的な比較をすることが非常に困難になっています。「この製品は素晴らしい」という情報は、全てビジネスに参加している紹介者からしか得られないのです。
3-5. 疑惑5:運営会社の実態と過去の経歴は信頼できるか?
最後に、プロジェクトの舵取りを行う運営会社と、その創業者について見ていきましょう。
3-5-1. 運営会社Vyvo Internationalの沿革と、過去のビジネスモデルからの変遷
Vyvo社は、過去にも「Helo」というブランド名で、類似の健康管理ウェアラブルデバイスを用いたMLMビジネスを展開していました。inPersonaは、そこにWeb3やNFTといった新しい要素を加えてリブランディングしたプロジェクトと見ることができます。
3-5-2. 創業者Fabio Galdi氏の経歴と、過去のプロジェクトの評判
創業者であるFabio Galdi氏は、過去に複数のIT系企業を立ち上げたシリアルアントレプレナーです。しかし、彼が過去に関わったプロジェクトの中には、そのビジネスモデルの持続可能性について、海外の掲示板などで否定的なレビューや議論が交わされているものも存在します。
これらの5つの疑惑は、inPersona(Vyvo)が単なる「未来の健康プロジェクト」ではない、複雑でハイリスクな側面を持っていることを強く示唆しています。
次の章では、これらの疑惑を、日本の法律という観点からさらに深掘りしていきます。
4.【法的検証】inPersona(Vyvo)は「ねずみ講(無限連鎖講)」にあたるのか?
前の章で浮かび上がった数々の疑惑。これらを見て、多くの人が抱く最大の疑問は「これって、結局のところ、ねずみ講じゃないの?」ということでしょう。
この問いに白黒をつけることは、あなたの資産と人間関係を守る上で極めて重要です。なぜなら、日本では「ねずみ講」は法律で明確に禁止された犯罪行為である一方、「MLM(マルチ商法)」は厳格な規制のもとで合法的なビジネスとして認められているからです。
この章では、法律という客観的な物差しを使い、inPersona(Vyvo)がどちらに分類されるのかを徹底的に検証します。
4-1. 日本の法律における「MLM(連鎖販売取引)」と「ねずみ講」の明確な定義
まず、両者の法的な定義を正確に理解しましょう。
- ねずみ講(無限連鎖講):
- 根拠法: 「無限連鎖講の防止に関する法律」
- 定義: 製品やサービスの販売・提供がほとんど介在せず、新規会員を勧誘し、その会員が支払う会費や加盟金といった金品を、上位会員で分配することによって成り立つ組織。後から参加した人が、構造的に必ず損をすることが運命づけられているため、法律で全面的に禁止されている犯罪です。
- MLM(マルチ商法/連鎖販売取引):
- 根拠法: 「特定商取引法(特商法)」
- 定義: 商品やサービスを販売しながら、同時に購入者を販売員として勧誘し、ピラミッド型の販売組織を拡大していくビジネスモデル。勧誘した販売員の売上の一部が、紹介者の利益となる仕組みです。実態のある商品の流通があるため、合法的なビジネスとして認められていますが、強引な勧誘などを防ぐため、特商法によって厳しく規制されています。
両者を分ける決定的な境界線は、「実態のある商品の流通があるか、ないか」、そして**「主な収益源が、商品の販売利益か、会員からの加盟金か」**という点です。
4-2. Vyvoのビジネスモデルを法律の条文に当てはめてみる
では、この定義をinPersona(Vyvo)のビジネスモデルに当てはめてみましょう。
Vyvoのケースでは、「Vyvoスマートウォッチ」と「データNFT」という、**形のある「商品(または権利)」が明確に存在します。**参加者は、これらの商品を購入し、その上でビジネス活動を行います。
この一点において、商品が全く介在しない「ねずみ講」の定義からは外れる、と解釈するのが一般的です。
しかし、問題は、その**「商品」の価値と、報酬体系の「バランス」**にあります。
前の章で検証したように、
- スマートウォッチの性能は、本当にその価格に見合っているのか?
- データNFTの数十万円という価格に、客観的な価値はあるのか?
- 参加者が得る報酬の大部分は、「健康データをマイニングした利益」なのか、それとも「新規会員を高額なNFTと共に紹介したことによるボーナス」なのか?
もし、多くの参加者の収益源が、後者の「勧誘ボーナス」に大きく依存しているとすれば、それは**「商品の販売を隠れ蓑にした、実質的なねずみ講ではないか」**と疑念を抱かれる、極めてグレーな状態と言えます。
4-3. 結論:「製品」が存在するため、現行法で「ねずみ講」と断定するのは困難。しかし…
これらの点を踏まえると、inPersona(Vyvo)のビジネスモデルを、現行法で直ちに**「ねずみ講」として立件・処罰することは、極めて困難**であると言えます。「商品」が存在するという形式上の要件を満たしているからです。
しかし、法律上『ねずみ講ではない』ということが、『安全である』『健全である』『儲かる』ということを一切意味しない、という事実は、絶対に忘れてはなりません。
inPersona(Vyvo)は、法律上は「連鎖販売取引(MLM)」に分類される可能性が非常に高いビジネスです。そして、その中でも、高額な初期費用を伴い、報酬における勧誘の比重が大きいと見られることから、消費者トラブルに発展しやすい、極めてハイリスクなモデルであると、私たちは評価します。
法律という物差しだけでは、このビジネスの全てを測ることはできません。
次の章では、実際に参加した、あるいは勧誘された人々の「生の声」を集め、inPersona(Vyvo)のリアルな評判と実態に迫ります。
5. inPersona(Vyvo)のリアルな評判と口コミ
法律論や理論だけでは、このビジネスの本当の姿は見えてきません。最も価値があるのは、実際に参加している人、そして離脱した人たちの「生の声」です。
ただし、インターネット上の情報は玉石混交です。この章では、賞賛の声と批判の声を公平に紹介すると同時に、あなたがその情報を**「どのように読み解くべきか」**という、情報リテラシーの視点も提供します。
5-1.【賞賛の声】:X(旧Twitter)や紹介者ブログに見られる成功者の主張
X(旧Twitter)や、個人のブログで「#inpersona」「#vyvo」と検索すると、ビジネスの成功をアピールする、きらびやかな投稿が数多く見つかります。
【よく見られる主張】
- 「権利収入で自由な生活を手に入れました!」
- 「Web3の最先端!この波に乗らないのはもったいない!」
- 「素晴らしい仲間たちと、毎日ワクワクしながら活動しています!」
- 報酬画面のスクリーンショットや、高級ホテルでのセミナーの様子を写した写真
これらの投稿は、夢と希望に満ちており、プロジェクトの成功を強く印象付けます。
【読む際の注意点】
これらの情報を鵜呑みにする前には、一度立ち止まって考える必要があります。
- ポジショントークの可能性: 発信者の多くは、あなたを勧誘することで直接的な利益を得る立場にある**「アップライン」**です。彼らの発言には、ビジネスの魅力的な側面だけを強調し、リスクやデメリットを意図的に語らないという、強いバイアスがかかっていることを前提に読む必要があります。
- 生存者バイアス: 成功談を語るのは、当然ながら、うまくいっているごく一部の人だけです。その輝かしい成功の裏には、期待したほど稼げず、声も上げずに静かに辞めていった、より多くの参加者が存在する可能性を忘れてはいけません。
5-2.【批判の声】:国民生活センターへの相談事例、Yahoo!知知恵袋、暴露系YouTuberの指摘
一方で、検索窓に「Vyvo 怪しい」「Vyvo マルチ」と入力すると、全く逆の、批判的な意見や相談が数多く見つかります。
【よく見られる指摘・相談内容】
- 国民生活センターや消費者庁への相談:inPersona(Vyvo)に名指しした注意喚起は(2025年7月現在)出ていませんが、「モノなしマルチ」「サイドビジネス商法」といった手口に関する相談は後を絶ちません。「説明された内容と実態が違う」「儲かるどころか借金だけが残った」「友人関係が壊れた」といった悲痛な声が、典型的な相談事例として挙げられています。
- Yahoo!知恵袋:「友人からinPersonaに勧誘されたのですが、これはねずみ講ではないですか?」「VSCトークンは本当に換金できるのでしょうか?」といった、勧誘された側の素朴な、しかし核心をつく質問が数多く投稿されています。そこには、第三者からの客観的な意見を求める、切実な不安が表れています。
- 暴露系YouTuberの指摘:ビジネスモデルの矛盾点や、トークン価格の下落、創業者の過去の経歴などを掘り下げ、プロジェクトの危険性を告発する動画も存在します。彼らは、報酬体系が新規参入者の資金に依存しているポンジ・スキーム的な構造であると強く批判しています。
5-3. 元参加者・離脱者が語る、組織内部の実態
最も貴重な情報は、実際に組織内部にいた元参加者や、途中で離脱した人々の体験談です。ブログやSNSの投稿を総合すると、以下のような共通したストーリーが浮かび上がってきます。
- 【勧誘期】夢のような話と熱狂的なセミナー「すごい人がいる」「人生が変わる」と、最初は期待感に満ちたセミナーや勉強会に誘われる。アップラインの成功者の華やかな生活を見せられ、「自分もこうなれる」と夢を見て、高額な初期費用を支払う。
- 【活動期】友人・知人のリストアップと勧誘へのプレッシャー活動が始まると、まずは友人や知人、家族のリストアップを指示される。「相手のためになることだから」と教え込まれ、SNSやリアルでの勧誘活動を行うよう、アップラインから常にプレッシャーをかけられる。しかし、思うように成果は上がらない。
- 【現実期】期待外れの報酬と人間関係の悪化「歩くだけで稼げる」はずだった報酬(VSCトークン)は、トークン価格の下落もあり、初期投資を回収するには程遠い金額。主な収入源は、やはり誰かを勧誘することだと気づく。強引な勧誘が原因で、大切な友人から距離を置かれ、人間関係が悪化していく。
- 【離脱期】静かに消えていく人々高額なセミナー代や月々の費用だけがかさみ、精神的にも金銭的にも疲弊。アップラインに相談しても「あなたの努力が足りないからだ」と言われ、誰にも相談できずに、静かにビジネスから離脱していく…。
もちろん、これは一部の体験談かもしれません。しかし、公式の華やかな成功物語の裏側には、このような厳しい現実が存在する可能性も、あなたは知っておくべきです。
賞賛と批判、そして内部からのリアルな声。
これらの情報を踏まえた上で、もしあなたが実際に勧誘された場合、どのように振る舞うべきでしょうか。
次の章では、あなたの身を守るための、具体的な質問リストと断り方について解説します。
6. もしあなたが勧誘されたら。その場で使える質問リストと断り方
これまでの章で、inPersona(Vyvo)のビジネスモデルと、それに伴うリスクの全体像が見えてきたはずです。しかし、知識だけでは不十分です。友人や知人から熱心に勧誘された時、その場の雰囲気や人間関係に流されず、冷静に対処するための「実践的な武器」が必要です。
この章は、あなたが勧誘の場で思考停止に陥らず、自分の頭で判断し、そして自分の足でしっかりと立つための、具体的な会話術と護身術です。
6-1. 勧誘者に直接ぶつけるべき10の質問リスト
相手の熱意に押されそうになった時、以下の質問を冷静に投げかけてみてください。これらの質問は、相手が語る「夢」を、具体的な「現実」へと引き戻す力を持っています。相手がこれらの質問に明確に、誠実に答えられない場合、その話は聞くに値しない可能性が高いでしょう。
- これは、日本の法律(特定商取引法)における**「連鎖販売取引」に該当しますか?** YesかNoで、まずはお答えください。
- このスマートウォッチは、同価格帯のApple WatchやFitbitと比べて、客観的に何が優れているのですか?
- このデータNFTの価格(例:約24万円)の、客観的な価値の根拠は何ですか?第三者の市場で自由に売買できるのですか?
- 報酬であるVSCトークンは、現在、日本の金融庁が認可した取引所では扱われていませんが、**具体的に、どのような手順で日本円に換金するのですか?**その際の手数料は正確に何パーセントですか?
- あなたの現在の収入のうち、純粋に製品を販売した利益と、新しい会員を勧誘したことによるボーナスの割合は、具体的に何対何ですか?
- このビジネスに参加した人の中で、**初期費用(数十万円)をすでに回収できた人は、全体の何パーセントくらいですか?**具体的なデータを見せていただけますか?
- あなたが考える、このビジネスの最大のリスクは何ですか?アカウントBANやトークン価格の暴落以外に、どんな危険性がありますか?
- 契約した場合、特商法で定められている**20日間のクーリング・オフ制度は適用されますか?**その手続きについて、今ここで書面で説明していただけますか?
- もし、明日から新規会員が一人も入ってこなくなったとしても、このビジネスモデルは持続可能ですか?
- このビジネスを始めることで、友人や家族を失うリスクについては、どのようにお考えですか?
6-2. 「すごい話だけど、一旦自分で調べてみるね」が最強の断り文句である理由
その場で契約を迫られたり、決断を急かされたりした場合、この一言があなたを守る最強の盾になります。
「すごい話だね!すごく面白いと思う。ただ、こういう大事なことは、一旦自分でちゃんと調べてから判断したいんだ。だから、少し時間をくれるかな?」
なぜ、この言葉が最強なのでしょうか?
- 相手を否定せず、関係性を壊さない:頭ごなしに「怪しい」「それはマルチでしょ」と否定すると、相手は心を閉ざし、人間関係に亀裂が入ります。まずは相手の話を一度受け止め、肯定する(「すごい話だね」)ことで、無用な対立を避けられます。
- あなたが「冷静な人間」であることを示せる:その場の雰囲気に流されず、「自分で調べる」という理性的な姿勢を示すことで、勧誘者は「この人は感情論では動かせないな」と察し、強引な勧誘をしにくくなります。
- 時間という最大の武器が手に入る:高圧的な勧誘の場から、一旦離脱することができます。そして、この記事で得た知識などを元に、冷静に情報を再確認し、自分の意思を固める時間を得られます。
もし、あなたがこの言葉を伝えた時に、相手が「調べる必要ないよ!」「今決断しないと損だよ!」と、あなたの**「調べる権利」を妨害しようとしてきたら、それは極めて危険なサイン**だと判断してください。
6-3. しつこい勧誘への対処法と、相談すべき公的機関
「調べてみる」と言っても、相手が引き下がらず、しつこく連絡してくる場合もあります。その際は、以下のステップで、きっぱりと対処しましょう。
- 明確な意思表示:「自分で調べてみた結果、私には向いていないと判断しました。なので、この話はここでお断りします。」と、はっきりと断りの意思を伝えます。
- 再勧誘の禁止を告げる:それでも勧誘が続く場合は、「特定商取引法では、一度断った相手に対して、再度勧誘することは禁止されています。これ以上の勧誘は、法律違反になる可能性があります。」と、冷静に伝えましょう。
- 公的機関に相談する:恐怖を感じるほどの勧誘や、脅しめいた言動があった場合は、ためらわずに以下の公的機関に相談してください。
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」:どこに相談していいか分からない場合、まずはこちらに電話してください。最寄りの消費生活センターなど、適切な相談窓口を案内してくれます。
- 国民生活センター・お近くの消費生活センター:契約トラブルや悪質商法に関する、専門の相談員がいる公的機関です。
- 警察相談専用電話「#9110」:事件性がある、身の危険を感じるなど、緊急性が高い場合はこちらに相談しましょう。
あなたの資産、時間、そして大切な人間関係を守れるのは、あなた自身だけです。
最後のまとめで、これまでの調査結果を総括し、あなたが取るべき最終的な行動を確認しましょう。
7. まとめ:全てのデータを踏まえて、あなたが今すぐ取るべき行動
私たちは、inPersona(Vyvo)が公式に語る「未来のビジョン」から始まり、その裏に潜む「5つの重大な疑惑」、法律という客観的な物差し、そして実際に参加した人々の生々しい口コミまで、このビジネスモデルをあらゆる角度から徹底的に検証してきました。
浮かび上がってきたのは、「健康になるほど豊かになれる」という美しいビジョンの裏で、実際には**「新規参入者が支払う高額な初期費用」**が、既存会員の報酬の大きな源泉となっている可能性が極めて高い、という厳しい現実です。
製品価値の客観的根拠の乏しさ、価値が不安定な暗号資産への依存、そして何よりも、ビジネスの主軸が「他人を勧誘すること」に置かれているように見える報酬体系。
これらは、あなたの賢明な直感が「怪しい」と感じ取った、まさにその正体です。
もしあなたが、友人関係を失うリスク、数十万円の初期費用を失うリスク、そして価値が不安定な暗号資産に未来を委ねるリスクを冒してまで、このビジネスにまだ魅力を感じるのであれば、私たちは止めません。決断するのは、あなた自身です。
しかし、この記事の全てのデータを踏まえて私たちが推奨する、あなたが**『今すぐ取るべき行動』**は、ただ一つです。
それは、「今は、手を出さない」そして、勧誘に対しては「きっぱりと断る」ことです。
なぜなら、あなたの貴重な時間、汗水流して稼いだお金、そしてこれまで築き上げてきた大切な人との信頼関係は、不確実でハイリスクなリターンのために危険に晒してよいほど、軽いものではないからです。
「簡単に儲かるうまい話」は、残念ながらこの世には存在しません。もし存在するとすれば、それは必ずどこかに、あなたが見過ごしているだけのリスクや、不都合な真実が隠されています。
この記事を通じて、あなたは単に一つのビジネスモデルについて詳しくなっただけではありません。甘い話の裏側を見抜く**『目』と、冷静に判断するための『知識』、そして毅然と断る『勇気』**を手に入れたはずです。
その力こそが、これからあなたの資産と人生を守る、最強の盾となるでしょう。


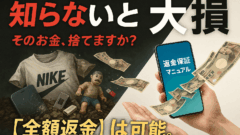
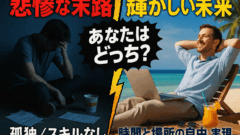
コメント