「ケーコジはもう稼げない」「規制強化で終わった」
ネット上に溢れるそんな声を真に受けて、あなたはまだ、スマホ代に毎月数千円も払い続けているのでしょうか?
はっきり言います。その「オワコン説」こそが、我々にとって最大のチャンスです。
2025年現在、ライバルが減った市場には、まだ「月5万円」を無風で抜き取る**“歪み”が残されています。それは、汗水垂らして働く労働ではありません。国の制度とキャリアの競争原理を利用し、SIMカードを入れ替えるだけで現金と最新iPhoneが手元に残る、現代に残された「錬金術」**です。
想像してみてください。
最新のiPhoneを実質タダで使い倒し、通信費は0円、さらに週末のちょっとした手間で、サラリーマンの小遣い以上の利益が口座に振り込まれる生活を。
ただし、無知は罪です。
かつてのような「適当な転売」は通用しません。無策で飛び込めば、一発でブラックリスト(BL)行きとなり、二度と携帯契約ができなくなるリスクもあります。
この記事では、**2025年の最新規制に対応した「ブラックリスト回避の鉄則」から、利益を最大化する「MNPループの全手順」**まで、ショップ店員が口を閉ざす裏ルールをすべて公開します。
スマホはもう、「買う」ものではありません。「回して」稼ぐ資産です。
さあ、情弱(カモ)を卒業し、搾取する側へと回る準備はできましたか?
1. 【現状分析】ケーコジ(携帯乞食)とは?規制強化後のリアルな収支
「ケーコジは終わった」「もう稼げない」
SNSやネット掲示板でこのような言葉を見かけるたびに、私は心の中でほくそ笑んでいます。なぜなら、大衆が撤退した市場こそが、最もイージーに利益を抜ける場所だからです。
結論から言えば、2025年現在でもケーコジは**「月5万円」程度であれば、極めて低い労力で稼ぎ続けることが可能**です。ただし、やり方は大きく変わりました。まずは、ケーコジの正体と、今の「稼ぎの構造」を解剖します。
1-1. ケーコジの定義:MNP(乗り換え)特典と端末売却益のアービトラージ
そもそも「ケーコジ(携帯乞食)」という言葉は蔑称のように聞こえますが、やっていることは立派な経済活動、すなわち**「アービトラージ(裁定取引)」**です。
通常、スマホを契約するときは「定価」で端末を買い、「定価」で通信費を払います。しかし、ケーコジは違います。
-
**他社からの乗り換え(MNP)**という強力なカードを切る。
-
キャリアが提示する**「巨額の割引」や「キャッシュバック」**を引き出す。
-
手に入れた端末を市場価格で売却、あるいはポイントを現金化する。
-
**「得られた利益 > かかった経費(通信費・手数料)」**の状態を作り出す。
この**「歪み」**を意図的に作り出し、差額をポケットに入れる行為。これがケーコジの定義です。2025年のケーコジは、単に端末を転売するだけでなく、回線契約に伴う「ポイント還元」や「維持費の圧縮」までを含めた、通信費のトータルマネジメントへと進化しています。
1-2. なぜ儲かるのか:キャリアのシェア争いと代理店インセンティブの構造
「なぜ、たかが乗り換えで数万円も貰えるのか? 怪しい裏があるのでは?」
そう思うのも無理はありません。しかし、これには携帯業界特有の**「カネの流れ」**が関係しています。
大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)にとって、最も欲しいのは**「他社からの顧客奪取」**です。市場は飽和しており、新規顧客はもう増えません。ライバルの客を奪うしかないのです。
ここで登場するのが**「販売代理店」**(街の携帯ショップや家電量販店のカウンター)です。
-
キャリア: 「他社から客を奪ったら、代理店に報酬(インセンティブ)を払うよ」
-
代理店: 「今月あと10件契約しないと、キャリアからの報酬が貰えない(あるいはランクが下がる)!」
-
代理店: 「赤字でもいいから、客に2万円キャッシュバックして契約してもらおう!」
この**「代理店がノルマ達成のために吐き出す販促費」**こそが、ケーコジの収益源です。つまり、私たちは代理店のノルマ達成を手助けし、その対価として報酬を受け取っているのです。この構造が崩れない限り、ケーコジが完全に消滅することはありません。
1-3. 【2025年最新データ】「一括1円」規制後のトレンドは「実質24円+ポイント還元」
かつては「iPhone一括1円(返却不要)」という異常な時代がありました。しかし、総務省の規制強化により、「値引きの上限」が厳格化されました。では、2025年の今はどうなっているのでしょうか。
トレンドは明確に以下の2つにシフトしています。
-
「一括」から「実質(レンタル)」へ
-
端末を「買う」のではなく「2年レンタル(実質24円など)」で契約する案件が主流。
-
端末売却益は出せませんが、**「最新iPhoneを2年間タダ同然で使い倒す」**ことで、本来かかるはずだった10万〜15万円の出費をゼロにします(支出削減=利益)。
-
-
「端末値引き」から「SIM単体キャッシュバック」へ
-
端末を買わず、SIMカードのみをMNPで契約する「SIM単(シムタン)」案件。
-
これには規制の抜け道があり、2万円〜3万円相当のポイント還元が頻繁に行われています。
-
現在のケーコジの最適解は、**「自分用の端末はレンタルで激安運用し、利益用の回線はSIM単体契約でポイントを稼ぐ」**というハイブリッド型です。
1-4. 収支シミュレーション:iPhoneレンタル+SIM単体CBで利益を出す計算式
では、実際にどれくらい利益が出るのか、2025年の典型的な「SIM単体」案件を例にシミュレーションしてみましょう。
【ケーススタディ:大手キャリアのサブブランドへのMNP(SIM単体)】
量販店の週末イベントなどでよくある「MNPで20,000ポイント還元」という案件を狙った場合です。
| 項目 | 金額・内容 | 備考 |
| ① 収入(メリット) | 20,000円分 | 家電量販店ポイントやPayPayなど |
| ② 支出(イニシャル) | 3,850円 | 契約事務手数料(※Webなら無料の場合も) |
| ③ 支出(ランニング) | 約7,700円 | 月額1,100円 × 7ヶ月維持(ブラックリスト回避用) |
| ④ 支出(MNP弾費用) | 約3,000円 | 日本通信などで弾を作成した費用 |
| 合計収支(①-②-③-④) | +5,450円 | 純利益 |
「えっ、たった5,000円?」と思いましたか?
しかし、これは**「1回線あたり」**の数字です。
もし、あなたが:
-
家族4人分で動けば、利益は一瞬で21,800円。
-
同時に「iPhone実質24円」を契約すれば、本来15万円する端末代が浮くため、経済的効果は17万円オーバー。
-
さらに、余った回線で「ポイ活アプリ」を回せば、利益は毎月積み上がります。
このように、「1撃のデカさ」ではなく「数と継続」で月5万を積み上げるのが、2025年式ケーコジのリアルな勝ち方なのです。次章では、この利益を生み出すための「準備」について解説します。
2. ケーコジを始めるための「必須準備」と「MNP弾」の製造
利益が出る案件を見つけても、それを撃ち落とすための「弾(たま)」がなければ指をくわえて見ているしかありません。ケーコジにおける「弾」とは、乗り換え(MNP)特典を受け取るためだけに契約し、即座に他社へ放出するための格安回線のことです。
ここでは、最短・最安でこの「弾」を製造し、戦場(店舗)へ向かうための準備を整えます。
2-1. 3種の神器:本人確認書類(マイナンバー)、クレジットカード、MNP予約番号
まず、ケーコジ活動を行う上で絶対に欠かせない「3種の神器」を揃えましょう。これらが一つでも欠けると、現場で契約を断られ、移動時間と交通費が無駄になります。
-
マイナンバーカード(必須級)
-
運転免許証でも契約は可能ですが、2025年のケーコジにはマイナンバーカードが必須です。理由は**「eKYC(オンライン本人確認)」の速度**です。弾となる格安SIMを即日発行する際、マイナンバーカードのICチップ読み取りなら審査が爆速で完了します。免許証の画像アップロードでは、審査に数日かかることもあり、商機を逃します。
-
-
本人名義のクレジットカード
-
デビットカードはNGです。弾を作るための格安SIM(MVNO)の多くは、デビットカードでの支払いを拒否します。年会費無料の楽天カードやPayPayカードで十分なので、必ずクレカを用意してください。
-
-
MNP予約番号
-
「現在契約中の電話番号」と「有効期限」が記載された10桁の番号です。現在は「MNPワンストップ方式(予約番号不要)」も普及していますが、量販店の現場ではシステムエラー回避のため、あえて予約番号を発行して持ち込むのがプロの作法です。
-
2-2. 「MNP弾」の最適解:日本通信、b-mobile、リンクスメイトのコスパ比較
「弾」は安ければ安いほど、最終的な利益が増えます。2025年現在、弾として優秀なのは以下の3社です。それぞれの特徴を理解して使い分けましょう。
| キャリア名 | プラン名 | 初期費用 | 月額維持費 | 特徴・評価 |
| 日本通信SIM | 合理的シンプル290 | 3,300円 | 290円 |
【コスパ最強】
維持費が圧倒的に安いため、弾を作ってから案件が見つかるまで「寝かせておく」のに最適。 |
| LinksMate | 音声通話プラン |
送料等込
約3,500円〜 |
517円〜 |
【速度最強】
「強制開通」オプションを使えば、申し込みからMNP予約番号発行までが最短即日〜翌日で完了。「今週末案件に行きたい!」という緊急時に重宝する。 |
| b-mobile | 990ジャストフィット | 3,300円 | 990円 |
【予備戦力】
日本通信と運営元は同じだが、審査基準が微妙に異なる場合があるため、日本通信がNGだった場合のバックアップとして機能する。 |
【結論】
基本は**「日本通信SIM」で安く弾を仕込み、急ぎで弾が必要な時だけ「LinksMate(リンクスメイト)」**を使うのが鉄板の立ち回りです。
2-3. 弾を作るタイミング:契約からMNP発行までのリードタイム(最短即日〜8日)
初心者が最も失敗するのが「タイミング」です。
「週末にすごい案件がある!」と気づいてから金曜日の夜に弾を作ろうとしても、物理SIMの配送が間に合いません。
-
eSIMの場合: 最短「即日」開通が可能(LinksMateなど)。ただし、MNP予約番号の発行には開通後さらに数時間〜1日かかる場合があります。
-
物理SIMの場合: 申し込みから到着まで「3日〜1週間」かかります。
【重要:8日ルールの壁】
一部の通信会社では、契約直後(8日以内)のMNP転出を制限している、あるいはシステム上予約番号がすぐに発行できない場合があります。
理想は、**「常に1〜2回線の弾(日本通信SIMなど)を契約済み状態でキープしておくこと」**です。月額290円なら、3ヶ月維持しても1,000円以下。案件を見つけた瞬間にMNP番号を発行し、即座に出撃できる体制こそが、機会損失を防ぐカギです。
2-4. 必要な初期費用:事務手数料と初月維持費の損益分岐点
最後に、弾作りにかかるコストを計算し、どれくらいの還元があれば「勝ち」なのかを把握しておきましょう。
【弾1発あたりの製造原価】
-
契約事務手数料:3,300円
-
初月月額料金:約300円〜1,000円
-
MNP転出手数料:0円(※現在は原則無料)
-
合計原価:約3,600円〜4,300円
つまり、乗り換え先の案件で**「5,000円相当以上の還元」**があれば、その時点でプラス収支が確定します。
現在の相場である「20,000ポイント還元」の案件に飛び込んだ場合、
-
20,000円(還元) − 4,000円(弾代) = 16,000円の純利益
これが1回線あたりの利益です。
初期費用として、弾を先に作るための現金(約4,000円×回線数)は必要ですが、これは確実に回収できる「投資」です。怖がらずに種を撒きましょう。
3. 【実践編】利益が出る「神案件」を探すリサーチ・ハッキング
「弾」の準備ができたら、次はそれを撃ち込む「場所」と「タイミング」の見極めです。
闇雲にショップを回っても、足が棒になるだけで利益は出ません。ケーコジのプロは、自宅にいながらX(旧Twitter)で情報を掴み、狙い撃ちで店舗に向かいます。ここでは、その具体的なリサーチ手法を公開します。
3-1. 狙うべき場所(狩場):家電量販店(ヨドバシ・ビック)vs 出張店舗(イオン・スーパー)
案件が見つかる場所は、大きく分けて「家電量販店」と「出張店舗(サテライト)」の2つです。それぞれの特性を理解し、自分のレベルに合わせて使い分けましょう。
-
家電量販店(ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ等)
-
特徴: 圧倒的な在庫量とポイント還元が魅力。特にヨドバシやビックは、キャリアの値引きとは別に「店舗独自ポイント」を数万円分上乗せしてくれることが多いです。
-
攻略法: 「土日の朝一」が鉄則。ライバルが多く、整理券争奪戦になることも。店員の知識レベルが高いため、下手な嘘は通じません。正攻法で交渉しましょう。
-
-
出張店舗(イオンモール、ショッピングセンターの特設会場)
-
特徴: キャリアショップが週末だけスーパーの通路などに出店している形態。代理店独自のノルマが厳しく、「何が何でも契約を取りたい」という心理が働きやすい場所です。
-
攻略法: 「穴場」になりやすいのがここ。量販店で在庫切れの案件が、田舎のイオンでは山積みされていることもあります。店員との距離が近く、交渉次第で特典が上乗せ(ティッシュや洗剤から、商品券へ)されるケースも稀にあります。
-
【結論】
初心者はポイント還元が明確で手続きがシステム化されている**「家電量販店」から始め、慣れてきたらライバルの少ない「出張店舗」**を開拓するのが黄金ルートです。
3-2. 狙うべき時期:決算期(3月・9月)、年末年始、ゴールデンウィークの施策
携帯業界には、キャリアが「赤字を垂れ流してでも契約数が欲しい時期」が存在します。このビッグウェーブに乗るだけで、利益は倍増します。
-
3月(年度末決算):【最強】
-
1年で最も案件が過熱する時期。キャリア、代理店ともに年間のノルマ達成がかかっており、普段はあり得ない「投げ売り」が発生します。有給を取ってでも動くべき月です。
-
-
9月(中間決算):【準最強】
-
3月に次ぐ山場。特にiPhoneの新型発表(例年9月)と重なるため、**「旧型iPhoneの在庫処分」**が狙い目になります。
-
-
年末年始・GW(ゴールデンウィーク):
-
大型連休は集客のための施策が打たれます。家族連れをターゲットにした「複数台契約キャンペーン」が多く、家族全員でMNPするには最適です。
-
【週末の法則】
月に関わらず、案件が出るのは**「金曜日の夕方〜月曜日」**です。平日は施策が伏せられていることが多いため、活動は週末に集中させましょう。
3-3. 隠語の解読:「iPhone一括」「実質」「POPなし案件」の見抜き方
現場のPOP(広告)やSNSの情報には、特有の用語が使われます。これを読み間違えると、利益が出るどころか負債を抱えることになります。
-
「一括(いっかつ)」:
-
意味: 端末代金を全額支払い済みとして購入すること。
-
判定: 【大当たり】。「一括1円」なら、1円払えば端末は完全に自分のもの。即売却して利益確定が可能です。現在はPixelのaシリーズやAndroidのミドルレンジでよく見られます。
-
-
「実質(じっしつ)」:
-
意味: 「2年後に端末を返却するなら」安く済む、というレンタル契約。
-
判定: 【自分用なら勝ち】。売却益は出せませんが、最新iPhone(10万円超)を2年間数十円で使えるため、支出削減効果は絶大です。
-
-
「POPなし(ポップなし)」:
-
意味: 「転売ヤー」対策で、あえて好条件の看板を出していない状態。
-
攻略: 店員に**「他社からの乗り換えを検討しているんですが、表に出ていないキャンペーンはありますか?」**と単刀直入に聞く勇気が必要です。これができるかどうかが、上級者への分かれ道です。
-
3-4. X(旧Twitter)検索コマンド:リアルタイムで「手配師」と「在庫情報」を抜く技術
2025年現在、最強の情報収集ツールはX(旧Twitter)です。しかし、普通に検索しても業者の宣伝ばかりがヒットします。以下のコマンドを駆使して、ノイズを除去し「生の情報」を抜き出してください。
【基本の検索コマンド】
-
"機種名" + "一括" -bot-
(例:
"Pixel8a" "一括" -bot) -
BOTの自動投稿を除外し、リアルな購入報告を探します。
-
-
"MNP" + "施策" + "地域名"-
(例:
"MNP" "施策" "新宿") -
特定のエリアで現在行われているキャンペーンを絞り込みます。
-
【高度な検索コマンド(ハッキング)】
-
min_faves:10 "一括1円"-
「いいね」が10以上ついている投稿に限定。バズっている(=条件が良い)案件を効率よく見つけられます。
-
-
filter:images "MNP" "還元"-
画像付きのツイートのみを検索。店内のPOP画像をアップしている投稿をピンポイントで探し出し、店舗を特定します。
-
【手配師(てはいし)とは?】
X上には、店舗とは別に個人的に案件を斡旋する「手配師」と呼ばれる人物が存在します。「好条件を紹介する代わりにマージンを抜く」等のグレーな取引持ちかけてくることがありますが、初心者は絶対に手を出してはいけません。 個人情報の流出やトラブルの元です。まずは、上記の検索で「店舗の公式キャンペーン」を探すことに集中してください。
4. 【現場攻略】契約フローと店員との攻防(審査落ち対策)
案件を見つけ、店員に声をかけた瞬間から、見えない心理戦は始まっています。
「お客様、申し訳ありませんが……」
この言葉を聞いて絶望しないために、審査の裏側と店員との会話術をマスターし、涼しい顔で契約を勝ち取りましょう。
4-1. 「特価BL」と「総合的判断」の正体:CIC信用情報とキャリア独自リストの違い
審査落ちには2つの種類があります。この違いを理解していないと、対策が打てません。
-
CIC(信用情報機関)のブラックリスト
-
原因: クレジットカードやスマホ分割払いの「滞納」。
-
影響: 全キャリアで契約不可。端末の分割購入(ローン)ができなくなります。
-
対策: 滞納分を完済し、5年間待つしかありません。これは金融事故であり、ケーコジ以前の問題です。
-
-
キャリア独自のブラックリスト(通称:特価BL、総合的判断)
-
原因: 過去にそのキャリアで「短期解約」を繰り返した、あるいは「特価契約」を乱発したこと。
-
影響: 「定価なら契約させてやるが、割引(特価)は適用できない」と拒否されます。
-
店員の常套句: 「審査の結果、今回は**『総合的な判断』**によりお断りさせていただきます」。これが特価BLの死刑宣告です。
-
現状(2025年): 特にドコモとソフトバンクはAIによる判定が厳格化しています。「回転日数(契約期間)」と「契約回数」の管理が、ブラック回避の生命線です。
-
4-2. 店員へのNGワード:「転売目的ですか?」と聞かれた時の正解回答
昨今の店員は、転売ヤーを排除するための研修を受けています。何気ない雑談の中に「誘導尋問」が仕掛けられています。以下のNGワードは絶対に口にしてはいけません。
-
NGワード集:
-
「SIMロックは解除されていますか?」(売る前提の質問)
-
「未開封で持ち帰れますか?」(転売ヤー特有の要求)
-
「端末は使わないので、SIMだけ抜いていいですか?」(論外)
-
そして、核心を突く質問**「これ、転売目的じゃないですよね?」**への正解回答を用意しておきましょう。
-
【正解の返し】
-
「今使っている機種のバッテリー持ちが悪くなったので、2台目(サブ機)として家で動画視聴やゲーム用に使おうと思っています」
-
「子供(または親)に持たせるスマホを探していて、とりあえず私が契約者になろうかと」
-
ポイントは、**「自分で(または家族が)使う具体的な利用シーン」**を即答することです。オドオドしたり、回答に詰まったりすると、「転売疑い」のフラグが立ち、審査時間を不当に引き伸ばされる(=諦めさせる)嫌がらせを受ける可能性があります。堂々と、一般客を演じきってください。
4-3. コンテンツ加入条件の損得計算:有料オプション即解約のリスク管理
「この2万円キャッシュバックを受けるには、月額2,000円の動画サービスと、セキュリティパックへの加入が必須です」
こうした「抱き合わせ商法」は今も健在です。ここで重要なのは、「即解約のリスク」と「損益分岐点」の計算です。
-
キャリア公式オプション(保証・通話定額など):
-
対処: 契約翌日や翌月にマイページから解約でOK。ただし、契約当日の解約はシステムエラーや店員へのペナルティになる可能性があるため、最低でも翌日まで待つのがマナーであり安全策です。
-
-
外部有料コンテンツ(動画サイト・アプリ課金など):
-
対処: これらは初月無料でない場合が多く、維持すると利益が削られます。
-
計算式:
(コンテンツ月額 × 必須維持月数) < 還元額ならGOサインです。-
例:月額500円×3個(1,500円)を加入条件に、5,000円還元が増えるなら、3,500円のプラスなので加入すべきです。
-
-
注意: 解約忘れが最大のリスクです。カレンダーアプリに「〇月〇日 コンテンツ解約」と通知を設定し、絶対に忘れないようにしましょう。
-
4-4. 開通テストと「開封の儀」:新品未開封で持ち帰るための交渉術(※現在は困難)
かつては「プレゼント用なので未開封で」という交渉が通じましたが、2025年現在、「新品未開封」での持ち帰りは99%不可能だと思ってください。
キャリア側も転売対策として、以下の手順(開封の儀)を必須化しています。
-
外箱のシュリンク(ビニール)を破る。
-
端末の電源を入れ、通信テストを行う。
-
箱にマジックで名前を書く、スタンプを押す(※一部店舗)。
【現在のリアルな攻略法】
無理に「未開封」を要求すると、転売認定されて契約自体を断られます。ここは潔く開封を受け入れましょう。
-
買取価格への影響:
-
実は、買取店側もこの状況を理解しています。「通電済み・開封済み」であっても、端末の保護フィルムさえ剥がしていなければ、「新品同様品」として高値で買い取ってくれる店がほとんどです。
-
-
現場での抵抗:
-
「箱への記名」だけは、買取価格が数千円下がるため全力で回避したいところです。「プレゼントで箱も取っておきたいので、記名だけは勘弁してもらえませんか?」と、下手に・丁寧に頼み込むのが唯一の対抗策です。それでもダメなら、利益が減ることを計算に入れた上で受け入れるしかありません。
-
5. ブラックリスト(BL)入りを防ぐ「回線維持・解約」の鉄則
契約が完了して端末とポイントを手に入れたからといって、すぐに解約するのは自殺行為です。
キャリアはあなたの行動を監視しています。ルールを破れば「ブラックリスト(BL)」入りし、今後数年間、一切の契約ができなくなります。ここでは、利益を守りながら安全にエグジット(解約・他社転出)するための鉄則を伝授します。
5-1. キャリア別・短期解約のデッドライン(180日・210日ルールの現在地)
かつては「90日維持すればOK」と言われた時代もありましたが、2025年現在の防衛ラインは明確に伸びています。
結論から言います。**「開通日を含めず、最低でも181日(約6ヶ月)〜211日(約7ヶ月)」**維持してください。
| キャリア | 危険水域(即BL) | 安全圏目安 | 最新傾向・注意点 |
| docomo | 90日未満 | 180日以上 | 最も厳しい。「特価BL」に入ると解除されるまで数年〜永久にかかるケースも。 |
| au / UQ | 120日未満 | 211日以上 | 以前は緩かったが、AI審査導入により厳格化。月末締めで計算し、余裕を持って7ヶ月維持が推奨。 |
| SoftBank / Y!m | 180日未満 | 181日以上 | 「180日ルール」が鉄則。1日でも早いとアウト。 |
| 楽天モバイル | 短期解約 | 180日以上 | 「1年無料」終了後、短期解約への監視を強化中。 |
【重要:0GB維持の罠】
単に契約しているだけでは不十分です。**「通信履歴(ログ)」**がない回線は、「利用意思のない転売目的」とみなされ、期間を満たしていてもBL判定されるリスクがあります。月に一度はWi-Fiを切ってWebブラウジングや通話を行い、数MBのパケットを消費させる「通電作業」をルーティン化してください。
5-2. 回線維持費を極限まで下げるプラン変更テクニック(irumo、povo2.0等)
「半年も維持したら、月額料金で利益が消えるのでは?」
その通りです。だからこそ、契約直後(または翌月)に**「維持費が激安のプラン」**へ変更し、ランニングコストを極限まで圧縮します。
-
docomo回線の場合:
-
変更先: irumo(イルモ) 0.5GBプラン(月額550円)
-
タイミング: 契約初月は変更せず、翌月から適用されるように予約変更するのが無難です。これで半年維持しても3,300円で済みます。
-
-
au回線の場合:
-
変更先: **povo2.0(基本料0円)**へMNP(番号移行)
-
裏技: au本家からpovo2.0への移行は「ブランド変更」扱いですが、即座に行うとブラック認定されるリスクがあります。安全策を取るなら、au本家の最安プラン(スマホミニプラン等)で数ヶ月耐えるか、UQ mobileへ移行して維持費を下げるのが定石です。
-
注意: povo2.0は「180日間トッピング購入がないと強制解約」されるため、半年に一度200円程度のトッピング購入が必要です。
-
-
SoftBank回線の場合:
-
変更先: LINEMOベストプラン など
-
戦略: SoftBankは本家内での激安プラン変更が難しいため、Y!mobileやLINEMOへの番号移行を活用します。ただし、これも「契約後即移行」はブラックリスクが高いため、初月〜2ヶ月目は本家で維持し、3ヶ月目以降に移行するなどの分散投資が必要です。
-
5-3. 利益確定(エグジット)のタイミング:キャッシュバック着弾と端末売却の時期
「いつ利益を確定させるか」も重要です。焦るとすべてを失います。
-
キャッシュバック(CB)の着弾確認
-
店舗やキャンペーンによって、CBの付与時期は異なります(即日、翌月末、3ヶ月後など)。
-
鉄則: 「CBを受け取るまで絶対に回線を動かすな」。
-
解約はもちろん、プラン変更やSIMカードの差し替えすら、判定NGのトリガーになる場合があります。利益(ポイント・現金)が手元に来るまでは、石のように動かないのが正解です。
-
-
端末売却のタイミング
-
一括購入の場合: 即売却OK。ただし、ネットワーク利用制限が「△(分割中扱い)」だと買取額が下がります。クレカで一括払いした場合は、キャリアに連絡して「◯」反映を依頼してから売るのがベストです。
-
実質レンタル(24円)の場合: 売却してはいけません。2年後に返却が必要です。
-
5-4. 喪明け(BL解除)までの期間目安:ドコモ・au・ソフトバンク・楽天の傾向
万が一、ブラックリストに入ってしまった場合、いつ解除されるのでしょうか?これを「喪明け(もあけ)」と呼びます。
-
docomo: 【無期懲役】。一度「特価BL」に入ると、解消される明確な基準がありません。5年経ってもNGの報告多数。最も怒らせてはいけないキャリアです。
-
au: 約1年(365日)。比較的解除は早い傾向にありますが、過去に未納がある場合は長期化します。
-
SoftBank: 約1年(365日)。1年経過後に、安い端末(移動機物品販売)などで実績を作ると解除されやすいという噂もあります。
【結論】
一度BL入りすると、そのキャリアの「iPhone 1円」などの神案件に数年間参加できなくなります。目先の数千円をケチって短期解約するより、**「正規の期間維持して、次回も参加できる権利(信用)を守る」**ほうが、長期的な期待値(LTV)は圧倒的に高いのです。
6. 【出口戦略】端末・ポイントの現金化と税金対策
端末を手に入れ、ポイントが付与されたら、いよいよ収穫の時です。
しかし、ここで「どこで売るか」「どう使うか」を間違えると、利益の10%〜20%をドブに捨てることになります。ケーコジは、現金化して銀行口座に着金するまでがケーコジです。最後の詰めを誤らないための、プロの出口戦略を伝授します。
6-1. 端末売却ルートの比較:中華系買取屋(海峡・ドラゴン)vs フリマ(メルカリ)
手に入れたiPhoneやPixelをどこで売るべきか。初心者は思考停止で「メルカリ」に出しがちですが、これは悪手です。プロは「中華系買取屋」一択です。
-
メルカリ・ラクマ(フリマアプリ)
-
デメリット: 販売手数料(10%)、送料負担、梱包の手間、そして「客層の悪さ」。
-
特にiPhoneなどの高額商品は、購入後に「傷があった」と難癖をつけて返品・すり替えを行う詐欺リスクがあります。
-
計算例: 10万円で売れても、手数料1万円+送料で手残りは約8.9万円。
-
-
中華系買取屋(通称:海峡、ドラゴンなど)
-
メリット: 「買取価格が異常に高い」「即現金化」「手数料ゼロ」。
-
東京の池袋、新大久保、秋葉原などに拠点を構える、海外輸出を前提とした買取業者です。「海峡(モバイル一番など)」や「ドラゴン(買取一丁目など)」といった通称で呼ばれ、HPで毎日変動する買取価格を公開しています。
-
彼らは海外(中国・香港・中東)の相場で動いているため、円安の現在は日本の定価近く、時には定価以上で買い取ってくれることさえあります。
-
結論: 1円でも高く売りたいなら、**中華系買取屋に持ち込み(または郵送)**が正解です。メルカリの手数料分だけで、利益が数千円〜1万円変わります。
-
6-2. 赤ロム・ネットワーク利用制限△のリスクと買取減額基準
端末を売る際に必ず確認されるのが、IMEI(製造番号)に基づく「ネットワーク利用制限」の判定です。
-
◯(マル): 端末代金完済済み。
-
△(サンカク): 端末代金分割支払い中。
-
×(バツ): 支払いが滞り、通信機能がロックされた状態(通称:赤ロム)。
【2025年の買取事情】
-
iPhone: 市場価値が高いため、「△」でも減額なしで買い取る業者がほとんどです。
-
Android(Pixelなど): 「△」だと数千円〜1万円程度減額されるケースがあります。Androidを一括1円などで購入した場合は、キャリアに連絡してステータスを「◯」に反映させてから売るのが鉄則です。
【赤ロム保証のリスク】
買取屋に売る際、「もし将来的に×(赤ロム)になった場合、損害賠償(全額返金)します」という契約書にサインさせられます。分割払いを踏み倒して端末を売るのは犯罪(詐欺罪)ですし、自分がブラックリスト入りする原因になります。端末代の残債がある場合は、売却益から必ず完済しましょう。
6-3. ポイントの現金化:PayPay、au PAY、dポイントの出口(投資信託・現金化)
最近の案件は「現金キャッシュバック」ではなく「ポイント還元」が主流です。ポイントをコンビニでちまちま使っていては、資産形成になりません。**「ポイントを即座に金融資産、あるいは現金に変える」**のが、ケーコジ流の錬金術です。
-
dポイント(ドコモ系):【最強】
-
出口: SMBC日興証券(日興フロッギー)
-
手法: dポイントで株やETFを購入し、即座に売却することで、手数料わずかで「現金」として証券口座に出金できます。現金化の効率が最も良いルートです。
-
-
au PAY 残高 / Pontaポイント(au系):
-
出口: auカブコム証券
-
手法: Pontaポイントで投資信託を購入し、約定後に売却。これで現金化可能です。au PAY残高も、じぶん銀行経由で現金化できます(手数料が必要な場合あり)。
-
-
PayPayポイント(ソフトバンク系):
-
出口: PayPay資産運用
-
手法: ポイントのまま「疑似運用」で増やすか、PayPay証券でETFなどを購入して現金化。ただし、PayPayは経済圏の囲い込みが強く、純粋な現金化へのハードルは他社よりやや高めです。
-
「ポイントはポイントとして使う」という常識を捨ててください。現金に戻し、それを次のMNP弾の費用や端末代に充てることで、**「複利」**のようにケーコジ資金を回転させることができます。
6-4. 税金問題:雑所得20万円の壁と、ケーコジ活動費の経費計上(交通費・通信費)
最後に、避けて通れないのが税金です。
「バレないだろう」は通用しません。マイナンバーと紐付いた現代、派手に稼げば税務署は見ています。
-
20万円の壁(給与所得者の場合):
-
会社員の場合、給与以外の所得(利益)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。ケーコジを本気でやれば、20万円は数ヶ月で超えます。
-
-
所得の種類:
-
譲渡所得: 生活用動産(自分が使っていたスマホ)の売却は非課税ですが、営利目的(最初から転売目的)で繰り返すと**「雑所得」**とみなされます。ケーコジ活動は継続性があるため、雑所得として申告するのが安全です。
-
-
経費計上の重要性:
-
税金は「売上」ではなく「所得(売上 − 経費)」にかかります。
-
経費にできるもの:
-
MNP弾の作成費用(事務手数料・月額料金)
-
契約時の事務手数料
-
店舗までの交通費(電車賃・ガソリン代)
-
端末の購入代金
-
-
これらを領収書やExcelで管理し、利益から差し引くことで、課税所得を圧縮できます。
-
ケーコジは「ビジネス」です。どんぶり勘定ではなく、帳簿をつける習慣を持つことが、長く安全に稼ぎ続けるための最後の条件です。
7. 【超越編】AI×ケーコジ×ポイ活による収益最大化エコシステム
月5万の壁を超え、月20万、30万の世界へ到達するには、自分の足で店舗を回るだけでは限界があります。ここからは、「数」の力と「仕組み」で稼ぐ、上位1%の領域へご案内します。
7-1. 家族名義(利用者登録)フル活用による「5回線×人数分」のスケールメリット
ケーコジには「1人あたり同時契約5回線まで」というキャリアの壁が存在します。しかし、これを突破する唯一のチートコードが**「家族」**です。
-
スケーラビリティの暴力:
-
あなた1人:MAX 5回線
-
夫婦2人:MAX 10回線
-
4人家族(親含む):MAX 20回線
-
-
利用者登録制度の活用:
-
契約名義は「家族(妻や親)」でも、支払いは「世帯主(あなた)」のクレジットカードでまとめられるキャリアが存在します(docomo、auなど)。
-
あるいは、家族カードを発行して決済させれば、実質的な管理はあなたがすべて行えます。
-
-
案件の重複取得:
-
「お一人様1台限り」の激アツ案件も、家族を連れていけば**「4人で4台」**確保できます。1撃の利益が4倍になれば、労力は4分の1で済みます。家族を巻き込む際は、焼肉や回らない寿司で還元し、協力体制を盤石にしましょう。
-
7-2. 複数回線シナジー:TikTok Liteや紹介キャンペーン周回の「複垢運用」
手に入れたSIMカード(電話番号)を、ただ維持費を払って寝かせておくのは「罪」です。
それぞれのSIMは、アプリ経済圏において**「独立した別人」**として認証されます。これを活用しない手はありません。
-
TikTok Liteの招待ループ:
-
概要: 新規ユーザー招待で4,000円〜5,000円貰えるキャンペーン(※時期により変動)。
-
手法: 既存のスマホではなく、ケーコジで手に入れた「新しい端末」と「新しいSIM」を使えば、自作自演で招待報酬を無限回収することが技術的に可能になります(※Wi-Fiは切り、キャリア回線で接続することでIPアドレス分散が必須)。
-
威力: 10回線あれば、それだけで4〜5万円。維持費など一瞬でペイできます。
-
-
PayPay・メルカリ等の「初回クーポン」:
-
多くのアプリには「初回限定50%OFF」や「紹介ポイント」があります。
-
回線ごとにアカウントを作成し、日用品や食料を初回クーポンで買い回ることで、生活コストを破壊的に下げることができます。
-
【AIによる自動化の可能性】
現在、一部の上級者は、この「毎日のチェックイン(ポイ活)」作業を、スマホ自動化ツール(FRepやMacrodroid)や物理的なタップ装置で自動化させています。寝ている間に全回線がポイントを稼いでくる。これこそが現代の「マイニング(採掘)」です。
7-3. 端末レンタル(返却プログラム)の裏技:2年後の残価設定免除と破損リスクヘッジ
「2年後に返却なんて、自分のものにならないから損だ」
そう考えるのは素人です。金融リテラシーのある人間は、キャリアの返却プログラム(カエトクプログラム等)を**「プットオプション(売る権利)付きのリース」**として捉えます。
-
残価設定の免除(利益の確定):
-
iPhoneの市場価格が暴落しても、キャリアが設定した「残価(2年後の買取保証額)」での引き取りが約束されています。市場リスクをキャリアに押し付けられる最強のヘッジです。
-
-
故障時のリスクヘッジ(22,000円の天井):
-
通常、iPhoneを落下させて画面を割れば数万円の修理費がかかります。
-
しかし、返却プログラム利用時、故障していても**「最大22,000円(故障時利用料)」**を払えば残価の支払いは免除されます。
-
つまり、**「どんなにボロボロに壊しても、2.2万円払えばチャラにしてくれる」**という保険が含まれているのです。これを理解していれば、高額なAppleCareに入る必要すらありません。
-
7-4. 結論:ケーコジは「労働」ではなく「回線ポートフォリオ管理」と心得よ
ここまで読み進めたあなたなら、もう気づいているはずです。
ケーコジは「安く買って高く売る」だけの転売ビジネスではありません。
-
MNP弾回線(攻めの資産):利益を狩りに行くための鉄砲玉
-
維持回線(守りの資産):次回の契約審査を通すための信用スコア育成枠
-
アプリ運用回線(収益不動産):TikTok Liteやクーポンで日銭を稼ぐインフラ
-
レンタル端末(リース資産):最新ガジェットによるQOL向上と経費計上枠
これらを組み合わせ、**「回線ポートフォリオ(資産構成)」**を最適化するマネジメント業。それが2025年のケーコジの正体です。
「オワコン」と嘆く大衆を尻目に、あなたは淡々と回線を回し、システムの一部として利益を吸い上げ続けてください。
その先に待っているのは、通信費はおろか、生活費の呪縛からも解放された自由な未来です。
さあ、まずは今週末、最初の「弾」を作りに行きましょう。行動した者だけが、この果実を味わえます。


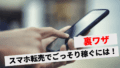
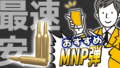
コメント